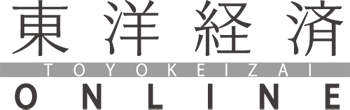帽子愛好家が信奉するカリスマの切り開き方 一筋30年のデザイナーが味わった挫折と奮起
glico氏:帽子を含むファッション全体の世界への最初の扉は、母と姉が開いてくれました。年の離れた姉は、私が小さい頃にはすでに、子ども服のデザイナーとして働いていたのですが、よく私にいろいろな服を着させてくれていたのです。周りとはひと味違ったファッションを見立ててくれる姉は私の自慢で、自然とデザイナーという職業が、私にとって憧れの対象になっていきましたね。
また、私の出身は名古屋なのですが、当時、洋書はまだ手に入りにくかった時代に、姉が『VOGUE』や『ELLE』などのファッション雑誌を、会社から持って帰ってきてくれていました。自分よりずっと歳上のオトナの雑誌をめくっては、その華やかな世界に想いを巡らせていましたね。自分も少しでも近づきたいと精一杯、だいぶ背伸びしておしゃれをしていたように思います。母親も、この業界にはいなかったものの、やはりファッションが好きで、よく私を街の帽子屋さんに連れて行ってくれていたんです。そうした中で、自然と、ファッションの世界全体への憧れを強くしていきました。
――華やかな世界への“憧れ”が出発点だった。

glico氏:そんな輝いて見えたファッションの世界の中で、特に「帽子のデザイナー」を意識するようになったのは、おしゃれに余念がなかった高校生の時、偶然入った帽子屋さんでの出来事がきっかけでした。お店の帽子をあまりに熱心に眺めていたからでしょうか、そこの方から「そんなに好きだったら、うちのお教室に来て作ってみない?」と、お店が開いている帽子教室に誘われたんです。
この時、人生ではじめて「自分で帽子をつくる」という体験をしました(70年代ファッションの中でも“フォークロア”が大好きだった私は、花柄をあしらった麦わら帽子を作りました)。それまで帽子は「買う」ものでしたが、教室で「作る」ことができたという達成感、実際に出来上がった帽子を手にとった時の、なんとも言えない“創作の喜び”のようなものが、心の内からこみ上げてきたんです。
「自分の好きだと思うものを作ることができる」。憧れだった世界が、急に現実味を帯びてきたようでした。ちょうど高校生活も後半に差し掛かっていた頃で、進路選択の時期でもあり、「東京に出て帽子の学校に通いたい。帽子のデザイナーになりたい!」と強く思うようになっていきましたね。
試行錯誤を重ね、みずからの“地図”を描く
glico氏:うちの親は放任主義でしたので、将来を決められるようなことはなかった代わりに、何でも自分で決めて進めなければなりませんでした。周りは大学や短大に進む友人が大半でしたが、帽子教室の先生や周りの大人にアドバイスをもらいながら、帽子を学べる学校も自分で探していました。学費も自前で用意する必要があったため、高校卒業後1年間は帽子屋さんでアルバイトとして働いていたんです。また、この時バイト先の帽子メーカーさんによくしていただき、進学先の東京での働き口も確保して、ようやく上京を果たしました。