かつて、大陸間を飛ぶ長距離便には4基のエンジンを持つ747や、3基を搭載したDC10といった機体が主に使われていた。これは、当時のエンジンの技術的な問題で、遠くへ飛ばすには3~4基のエンジンによる推力が必要だったほか、飛行中のトラブルでエンジンがひとつ止まってしまっても、残りのエンジンを使って飛行が続けられるというトラブル回避の理由もあった。逆にいうと、エンジン2基の機体では、万一の時に1基で飛び続けなくてはならず、それは「極めて危険なこと」と考えられていた。
ところが、エンジンの性能が過去20年ほどの間に向上した結果、エンジン2基の機体でも大陸間を楽々飛べるようになった。今年の夏ダイヤをもとに、米「USA Today」紙が発表した「長距離フライトランキングベスト25」によると、超ロングフライト上位の25区間のうち、エンジン2基のボーイング777は17区間を占めている。
エンジンの性能向上が進む一方で、地球温暖化につながる二酸化炭素(CO2)の削減が世界的に叫ばれるようになって来た。4発機は2発機に比べ燃料消費が多く、CO2や窒素酸化物(NOx)の排出量が大きい。それだけでなく、騒音レベルも高い。
これらの事情により、世界の多くの空港では、747などの4発機の乗り入れには懲罰的ともいえる高額の着陸料を課しているほか、極端な例では3発以上の機体の乗り入れを全面的に拒んでいる大阪国際空港(伊丹空港)さえもある。つまり、航空旅行の大衆化に大きく貢献した「ジャンボ機」は、いまや「できることなら飛んで来てほしくない機体」へとその立ち位置が変わってしまった。
それでも747のような大型機が持つ「1フライトでたくさんの乗客が運べる能力」は、航空会社にとって大きな魅力だ。1970年の747初就航以来、長期にわたってこれを超える乗客定員を持つ飛行機は出現しなかった。その後、1990年代になってようやくエアバス社が現在のA380の系譜に続く超大型機の開発に着手した。
ボーイング社はこれに追いつくため747改良型の投入を打ち出し、結果として747-8の生産にこぎ着けた。しかし、エアバス社が新しい超大型機に対し次々と新しい技術を盛り込んだのに対し、747改良型は「30年以上も前の古い型の飛行機がベース」と見なす航空会社が多く、受注実績は乏しいままに終わった。
新鋭機と比べ、燃料消費は1席当たり3割多い
在ロンドンの航空アナリストは「航空会社はいかに少ないコストで乗客を運ぶか。それが最大の課題だ」としたうえで、「747はもはや、うるさくて燃料を食う存在。閑散期に空席を埋めるのも航空会社にとって大きな負担」と指摘する。
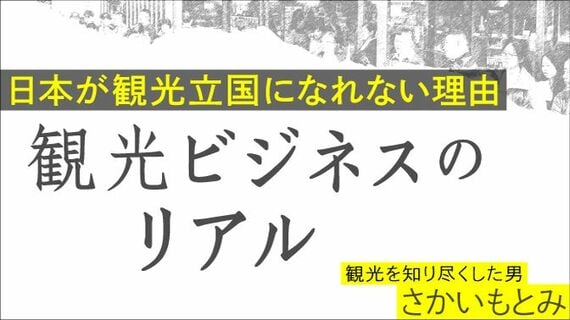
当のボーイング社自身も「この先、747や2階建て超大型機であるエアバスA380の需要が息を吹き返すことはないだろう(ランディ・ティンセス販売担当副社長)」と予測している。大型機を主要路線に投入し、大空港に利用客を集める「ハブ&スポーク」の手法はもはや時代遅れで、今後は一回り小さいながらも燃費の良いボーイング787やエアバスA350を使って、需要がそれほど大きくない区間をつなぐ「ポイントtoポイント」の直行便運航が求められる時代がやって来るとの見方が強い。
航空コンサルタント会社Leehamによると、たとえば、ロサンゼルス―ロンドン間での燃料消費は、747-8(405席と仮定)の場合約3万3000ガロン(1ガロンは約3.8リットル)だが、最新鋭機の787-9(290席)では1万8400ガロンにとどまるという。つまり、747はたとえ新型モデルでも最新鋭の2発機と比べ、1席当たりの燃料消費は30%も多いことになる。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら