能力ではなく「興味開発」こそ子育ての肝だ 「好きなことで自立する」を確実にするために
「もっと知りたい!」「やってみたい!」と人間が思う瞬間というのは、必ず心の中に「わあ!すごい!」という言葉が宿っているはずだ。言い換えれば「驚きと感動」を味わった瞬間に、人はその対象をもっと知りたい、もっとかかわっていたいと思うようになる。
子どもがピアニストになりたいと思うのは、名演奏を耳にして驚きと感動を味わったことがあるからだ。子どもがサッカー選手になりたいと思うのは、一流のプレーを目にして驚きと感動を味わったことがあるからだ。人は驚きと感動を味わうたびに、自分の興味の棚に引き出しをひとつ追加して、チャレンジすべき事柄かどうかの吟味を始める。
筆者自身は現在、わが子と教室へ通ってくる生徒を相手に、「わあ!すごい!」という言葉を引き出すべく格闘の日々を過ごしている。驚きと感動を届ける、あるいは一緒になって探すために、手を替え品を替えて授業を行っているが、その経験を通して見えてきたことがさらにある。それは「知識ではなくストーリーをひもとく」ということだ。
ストーリーこそが、関心を呼び起こす
数学や、歴史、科学、音楽、さらには絵画にも、様々な学問やテーマの中には驚きと感動が秘められている。ではそれを、どうすれば子どもたちに伝えられるのか? 一緒に共有できるのか? その答えが「ストーリー」なのだ。
たとえば、歴史はわかりやすい。年号や事件、名前を羅列して覚えるだけの歴史の授業を受けた読者は多いと思うが、そのような授業こそ「知識」を扱ってるだけなので、生徒は歴史に驚きと感動を感じられない。一方で、歴史小説や大河ドラマは「ストーリー」になっている。だからこそ、そこに驚きと感動を感じることができる。
人は「あらすじ」や「結末」という知識や情報を与えられるだけでは、感動はできない。ストーリーを自分で追体験するからこそ、その映画に感動する。同じことが教育や学習にも言える。子どもたちが自分で追体験できるようなストーリーを渡すこと、それこそが「驚きと発見」を届けるための一つの流儀なのだ。
「知識を詰め込む」という従来の教育を受け取ってきた親は、「私には無理だ!」と思うかもしれない。確かにこれは、決して容易なことではない。それでも、まずは近くにいる大人が「驚きと感動の種まき」にチャレンジしてみることからしか、始まらないのではないだろうか。
ここで『沈黙の春』で有名な、レイチェル・カーソンの言葉を引用したい。
筆者がこの言葉に出合ったとき、自分はそんな大人でありたいと思った。あなたはどうだろう? この世界の感動を分かち合うことは容易ではない。でも親であるあなたが、分かち合える大人であろうとしたら、子どもだけでなくあなた自身もチャレンジを始めることになるだろう。それは、親である私たちが心に秘めている、「好きなことを見つけてチャレンジする子どもを、育てる」というチャレンジだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


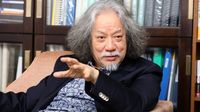




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら