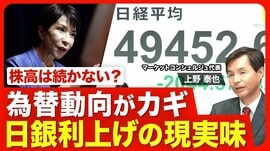「すきやばし次郎」の創業者で100歳のすし職人・小野二郎さん、これまでの軌跡やすしへのこだわり、すしを取り巻く環境の変化について語る
与志乃の親方の握ったすしの味を今でも覚えているという。「1番初めに行った時に、親父さんがすしをひと通り握ってくれた。そのうまさがものすごかった。今も忘れない。その時の穴子っていうのは本当にうまかった」と二郎さん。
特に穴子に塗るタレである「ツメ」が印象的で、「今思い出しても身震いするぐらいうまかった。味付けが桁違いにいい」。といっても、手取り足取り教えてくれるわけではない。その味をどうしても覚えようと、親方が不在の時にこっそりなめるなどして味や技術を身に付けてきた。「与志乃の親父さんは本当に腕がよかった」と言い、親方に追いつこうと腕を磨き続けてきた。「すきやばし次郎」の現店主で長男の禎一さん(66)によると、1965年に「すきやばし次郎」を開店してからも、時々思い出したように、当時の親方の握り方や、包丁さばきを二郎さんが語ることがあったといい、「追いつきたい、追い越したいという思いが父の中にずっとあったんだと思います」と話す。二郎さんが握るすしは、横から見ると「地紙形」といわれる、扇子の地紙のような扇形で、親方の握りを目指して長年かかってたどり着いたものだ。二郎さんは「自分の腕をまだ少し、もう少しと上げるように努力して変わっていくと、お客さんがほめてくれるんです」と話す。

「すきやばし次郎」の大きな特徴は、すし種や酢飯に手間をかけて理想的な温度ですしを一つ一つ順番に出せるよう、おまかせコースのようにしたことだ。
すしといえば、冷めたものが当たり前だったが、二郎さんは直前にご飯を炊いて冷まし、人肌程度に温かい酢飯を使う。「酢飯は人肌のほうがはるかにおいしい」と二郎さん。
また、すし種が酢飯に合うようにするにはどうしたらよいか、色々と研究したという。すし種の温度も、光ものは冷たく、ハマグリやアナゴは常温、クルマエビやアワビは温かくと大まかに三つに使い分ける。例えば、温かいアワビを使うのは、生のままでは硬くて口に入れた時に酢飯と一緒に食べようとしても、アワビだけ口の中に残ってしまうためだ。水と酒で煮て軟らかくし、ほんのりと温かい状態で握る。
クルマエビもゆでたてを握っている。以前はゆでたものを冷蔵庫に入れてから出していたので、冷たいものを使っていた。ある時、お客さんに「ちょっと食べてみて」とゆでて出したことがあり、好評だったため、それから温かくして、出すようになった。
温度だけでなく、すし種と酢飯のバランスも大切にしている。「口の中で、すし種と酢飯が同時に消えるとおいしく感じる」と禎一さん。酢飯は外側を固め、内側を柔らかめにふんわりと握り、その柔らかさは、握ったすしが客席の前の板に置かれた瞬間に酢飯が少し沈むほど。口に入れるとほどけて、すし種とともに消えていく。