一時的に赤字に陥ってもごはんのクオリティを守り、緻密なオペレーション設計や教育・研修制度で「できたてのおいしさ」と「手頃な価格でおなかいっぱい」を守るほっかほっか亭。
米の値段はある程度落ち着いてきており、価格調整やメニューそのものの見直しも進んでいる。2026年3月期は、堅調な数字が営業利益として出せる見込みだ。

ほっかほっか亭の強さの源泉はどこに?
改めて、ほっかほっか亭の強さの源泉はどこにあるのだろう。中途入社組の飯沼さんと信木さんは、売り上げ200億円規模の大企業ながら、「個人の裁量が極めて大きく、1人ひとりを尊重する」風土に驚いたという。
「やりたいと思えば、商品の企画からお客様に届くところまで。販促であれば、自分の企画したツールやデザインが店頭に貼られるまでを担当できます。それも、1人で全部担わなければいけないということではなく、社内外のさまざまなリソースを使い、素早く組み立てることができる」(飯沼さん)
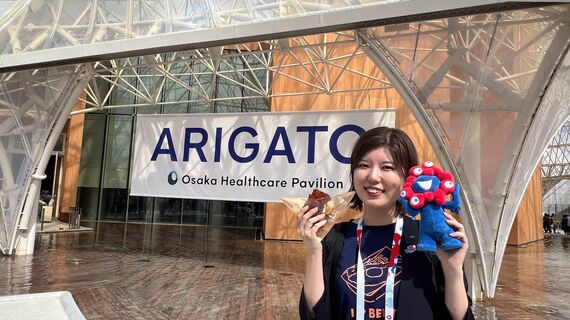
前編で触れた「創業時のフォント制作者探し」も若手デザイナーが発案し、すぐに飯沼さんが「とりあえずやってみよう」と承認。それがXで4400万ビュー、17万2000イイネを超えるバズを起こした。
社内には日々アイデアが飛び交い、若手も挑戦しやすい雰囲気が漂う。一方で、多様な人材の意見を融合させ、組織力を最大化するための仕組みづくりには課題も残る。それでも、「お客様に喜んでもらう」という共通の目的が、議論を前へ前へと推し進めている。
持ち帰り弁当の原点とも言えるその目的こそが、
成功の反対は失敗ではなく何もしないこと――。
次の50年も愛され続けるために、老舗弁当チェーンの進化は続く。

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら