日本初開催の"静寂の五輪"デフリンピックが実はスゴい! 観戦無料で日本の金メダル候補が多数、協賛には大手企業がズラリ…知られざる「全貌」
デフリンピックに出場できるのは、補聴器などを外した状態で、聞こえる最も小さな音が55dB(デシベル)以上の選手。
「55dBは普通の声での会話が聞こえない、という程度で、数字が上がるほどに聞こえない程度が上がります。100dBぐらいになると、ほぼ聞こえないようです」
パラリンピックの場合は障害の重度によって各競技でクラス分けがされているが、
「デフリンピックの場合、クラス分けはまったくありません。デフの選手は日常生活では補聴器などを付けて会話をする方も多いのですが、競技中は補聴器などを全部外すので、自身の聞こえ方に頼ることになります。ですから、選手間では聞こえ方にバラつきがあるんです。オリンピックでも身長や体重に差があっても同じ種目で戦っているように、“聞こえる差”がある中で勝負するのがデフリンピックのルールです。
ちなみに、選手たちから“あの人より聞こえないのに、同じ種目に出るのはおかしい”といった不満があがるような話は聞かないですね。一般的な大会に補聴器を付けて出場する選手もいますが、やはり出場条件が同じであるデフリンピックのほうがいい記録が出る、と話す選手も多いようです」

どの競技も“目で見える工夫”がなされている
今大会で開催されるのは21競技。『東京2020パラリンピック』では22競技だったので、ほぼ同数だ。オリンピックと同じく国際ルールが採用されているが、聞こえないことを補うため、各競技において“目で見える工夫”が施されている。
「水泳や陸上では通常、ピストルなどの音を合図にスタートしますよね。ただ、デフの選手はその音が聞こえにくい。そのため“スタートランプ”が使用されます。例えば陸上の100mの場合は、クラウチングスタートで顔を下げた状態の目線の真下にランプがあります。ランプの色が赤で“位置について”、黄色になったら“用意”、緑色に変わったら“スタート”です。走り出すタイミングが目で見てわかるようになっています。
立ったまま位置につく800mやマラソンでは少し離れたところに大きなランプがあり、選手たちはそれを見てスタートします。また、サッカーでは主審は笛だけでなく、旗も持ち、合図します。
バスケットボールではコートの端に『フラッグマン』というスタッフが配置され、笛やブザーの音に合わせて旗を振ります。空手やテコンドーはコートの4隅に置かれたライトが、審判員の合図に合わせて光ります。このように、音声の代わりに視覚的に情報を伝えるように工夫されています」



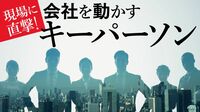





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら