フレンチの巨匠・三國シェフ「最初で最後」の家庭料理本に込めた食の哲学。インタビューで語った飽くなき探究心と家庭料理レシピに挑戦した理由
フランスではよく、「〇〇 ア・ラ・プロヴァンス(プロヴァンス風)」など、料理の説明をするメニュー名を使う。そこで、三國シェフもどんな料理かイメージできるように「長野の山奥でひとりでトマトを創っている 佐藤の母さんの甘くない酸味のきいた トマトのカルパッチョ カルダモンの薫り」などとする。
「今は甘くて柔らかい食材がもてはやされていますが、僕が子どもの頃は、酸味の効いたトマトを水代わりに食べていたんです。甘すぎるとそんな食べ方はできず、酸味をおいしいと思って僕は使っています。
生産者の名前を入れる方法は、その後デパートをはじめとして、多くの販売店やレストランで真似されるようになりました」と振り返る。
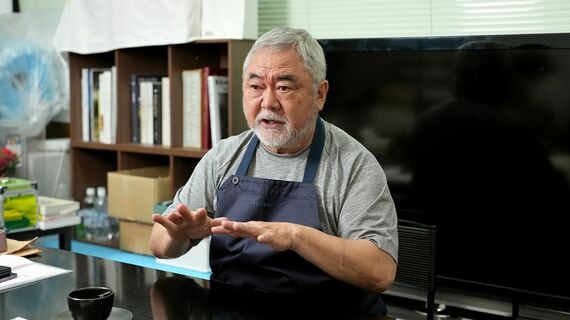
スローフードと食育への想い
1980年代にイタリアで始まり、すっかり浸透した「スローフード」の概念を持ち込んだことにも、三國氏は尽力していた。スローフードとは、環境や生産者に配慮した健康的な食を目指す社会運動で、ファストフードやジャンクフードに対抗する概念だ。
「編集者の小黒一三さんが創刊した『ソトコト』で一緒にスローフードを紹介しました。この概念を日本に持ってこよう、と言ったのは小黒さんです」(三國氏)。1999年に創刊した『ソトコト』は初期の頃、毎号のようにスローフード特集を組んでいた。
小黒氏との付き合いは、三國氏が帰国して間もない頃に始まっている。『ブルータス』(平凡出版、現・マガジンハウス)で編集者をしていた小黒氏が、「イッツ・ブルート」というコラムで三國氏を紹介。
これが縁で、三國氏が四谷で「オテル・ドゥ・ミクニ」を開業した翌年の1986年に刊行した、斬新な料理写真集『皿の上に、僕がある。』(柴田書店)に小黒氏は文章を寄せた。
その本が注目された結果、店は数カ月先まで予約で埋まり、三國氏は世界中の一流ホテルから乞われて、料理の腕を披露して回ることになった。「小黒さんが、僕を世に出したんです」(三國氏)。
スローフードとの出合いは、イタリアのスローフード協会が重んじる食育との出合いにつながった。
1999年、同協会のカルロ・ペトリーニ会長とフランスのワイン醸造学者のジャック・ピュイゼ氏に「本物の味覚を体験していない子どもが大人になれば、簡単に子どもを傷つける人間になりかねない。その前に、子どもの味覚を保護する教育をしよう」と誘われ、2000年から食育活動に取り組み始めたのだ。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら