「人は見た目が9割」「社会人は身なりが大事」を軽んじる人が知らない身だしなみの"本質"
もともとは、生まれに左右されない世界を目指したはずなのに、行き過ぎると、逆に、出生時点で差をつけるところに行き着く、というわけです。
ヤングの本の元のタイトルを、そのまま日本語に訳すと、「メリトクラシーの隆盛、1870年から2033年にかけての、教育と平等をめぐるエッセイ」です。私たちが生きている2020年代の日本は、まさにこのエッセイが予想した最終段階にあります。
もう、「メリトクラシー」ではなく、育ってきた環境や、それを用意してくれた家庭といった要素が重視されつつあります。あなたが得た能力=仕事が「できる・できない」を決めるのは、あなた自身の頑張りよりも、あなたが生まれ、育ってきた環境に(大きく)左右されていると言われています。
そればかりではありません。
社会学者の本田由紀は、「ハイパー・メリトクラシー」ということばをつくりました。ただ仕事ができるだけでは物足りない。人当たりがよく、周りに気遣いができ、面白い会話をしてといった、「コミュ力」が就職活動で求められているのが、その大きな特徴でしょう。
「人間力」とか「生き抜く力」といった表現は、ビジネス書の定番です。上司だって、「360度評価」と言われる周囲からの評価を常に意識しなければなりません。飲み会に誘うか誘わないかすら評判に影響します。
認識すべきなのは、SNSで「シゴデキ」とカタカナであらわされるような、なんとなくのイメージが、ひとり歩きしている状況です。仕事が「できる・できない」の基準がわからない。それは当然なのです。
ゲームだと割り切って淡々と仕事を
そこで提案です。
「ハイパー・メリトクラシー」の時代に特効薬はありません。それどころか、まともに向き合えば闇堕ちするしかない。闇ならまだしも、病む恐れも高い。
となれば、「できる」「できない」について、その線引きをはじめとして悩むかもしれません。あくまでもゲームだと割り切って、その会社のなかの基準を宝探しのように見つけようとする、そんなつもりで淡々とこなしましょう。
「メリトクラシー」の病はヤングが予言した以上に進んでいるからです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

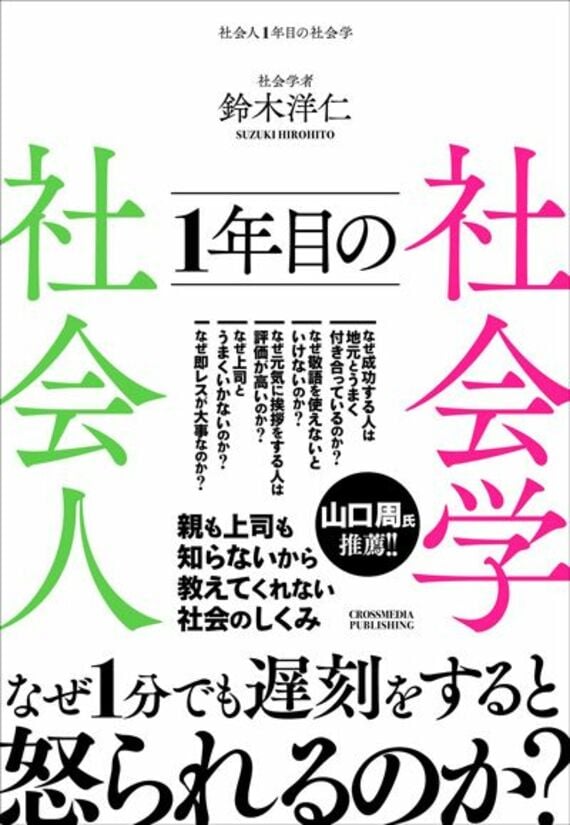






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら