「動物園のおさわりコーナーに連れていくと、同い年の子どもはたいてい怖がって触れないか、逆に強く当たってしまうことがあるんです。でも娘は、加減をよく理解しています。特に教えたわけではないのに、動物とのふれあい方を生まれながらにして理解しているみたい。それって、フクモモのおかげなのかなあって思うんです」
フクモモがつないだ縁
「僕は、フクモモと暮らし始めて、世界が広がったと感じています。フクモモつながりで、世代の違う友だちもできました。フクモモを飼っていなかったら、ブログもYouTubeもインスタもやっていなかったと思います」
2人が運営しているブログとYouTubeでは、理系夫婦として、エビデンスに基づいてフクロモモンガの飼い方や生態について解説している。
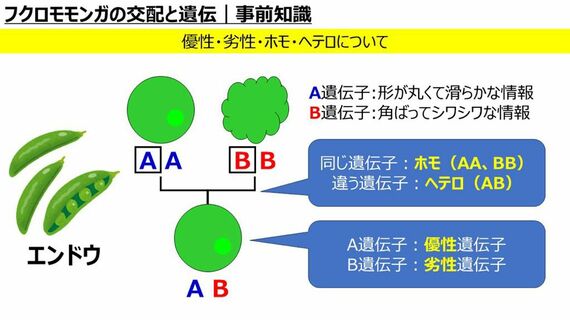

「当初は『フクモモの魅力伝え隊』という名前だったのですが、途中で名前を『もえひろ夫婦のフクモモLAB』に変えました。自分がジゲンを飼い始めたとき、情報があまりに少なくて、しかもエビデンスの怪しいものばかりだったんです。
フクロモモンガは、犬や猫と違い、野生の強い動物です。うまく共生していくために、エビデンスのある確かな情報を届けたいと思っています」
主に運営しているのは夫のひろさんだが、「もえひろ夫婦」と先にもえさんの名前を出すところに、彼の隠れた愛情を感じた。
「フクモモは僕に、家族や新しいつながりを運んできてくれました。僕にとっては『愛玩動物』ではなく、『一緒に生きる存在』なんです」
自分にとって、フクロモモンガがどんな存在なのか。言葉を選びながら、ひろさんが伝えてくれた。妻のもえさんが、「私よりも付き合いが長いもんね」とひろさんの顔を覗き込んで笑った。
小さな動物が、暗かったひろさんの部屋に明かりを灯す。その明かりに導かれるように、無数の縁がつながった。もえさんを結び、遠くの誰かとつながり、もふもふを中心に優しい輪ができる。その輪の中で、子どもたちが育っていく。殺伐とした世の中で育まれる、あたたかく手触りのある関係が、とてもまぶしく見えた。

・小動物飼育可の物件に住んでいること
・フクロモモンガ用のケージを用意し、寝床用のポーチ、止まり木、食器や給水ボトルを用意すること
・におい対策のためこまめにケージを掃除し、必要なら脱臭機を購入すること
・エサを食べなくなったら、別の種類のものをローテーションしながら与えること
・毎日必ず部屋んぽさせ、ストレスをためさせないこと
・排泄のしつけはできないことを受け入れること
・複数飼う場合、相性が悪ければケージを分けて飼育すること
・責任が持てなければむやみに繁殖させないこと
・野性に近い動物であることを理解し、心地よい距離を保って接すること
・10年以上、責任をもって飼育できること
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら