「課金しないとどうなるかな」→「バカだった…」と激しく後悔 ジャングリアに「ファストパスなし」で参加した男の哀れな末路
現状、国内のパークを見ると、それでも「課金した分は楽しめたな」(と少なくとも筆者は)思えることが多いが、どんどん課金額が積み上がり、顧客の期待値が上がっていったときに、息切れを起こさないかどうか。

また、ジャングリアについていえば事前の広告イメージや「ラグジュアリー」というイメージが先行し過ぎて期待値が上がり過ぎ、そこで足をすくわれた感も否めない。いずれにしても顧客期待値の上昇という問題が重くのしかかるのだ。



長期的な目線でみるとどう転ぶだろうか
2つ目は、長期的な目線、具体的にいえば「子ども客層」の先細りへの懸念だ。
すでに昨年話題になったように、特にディズニーランドに関しては小人の数が減っていることがファクトブックで報告されている。
確かに、値段が上がり過ぎれば子どもだけで行く、ということは容易ではなくなるし、ファミリーだったとしても、金銭的に厳しい家庭はどんどんパークから遠のいてしまう。
本来、子どもは未来の重要顧客であり、10年、20年後に彼らが親になったときに愛着のあるテーマパークにまた子どもたちを連れてくる……という流れができるはずだが、それが先細りしていくと、長期的にみて経営にどのような懸念があるのか(もっとも少子高齢化で何もしなくても子どもは減っていくから、それはそれでいいのかもしれない)。
富士急ハイランドの場合は、別にチケットの値段が上がるわけではなく、単にチケットのオプションが増えるだけだから、こうした懸念はお門違いかもしれない。しかし、昨今のテーマパーク事情と連動していることを踏まえるならば、富士急ハイランドも今後、このような問題と無関係ではいられなくなるのではないか。
テーマパークは金持ちのためだけのものなのかどうか。その分岐点に私たちは立っているのかもしれない。

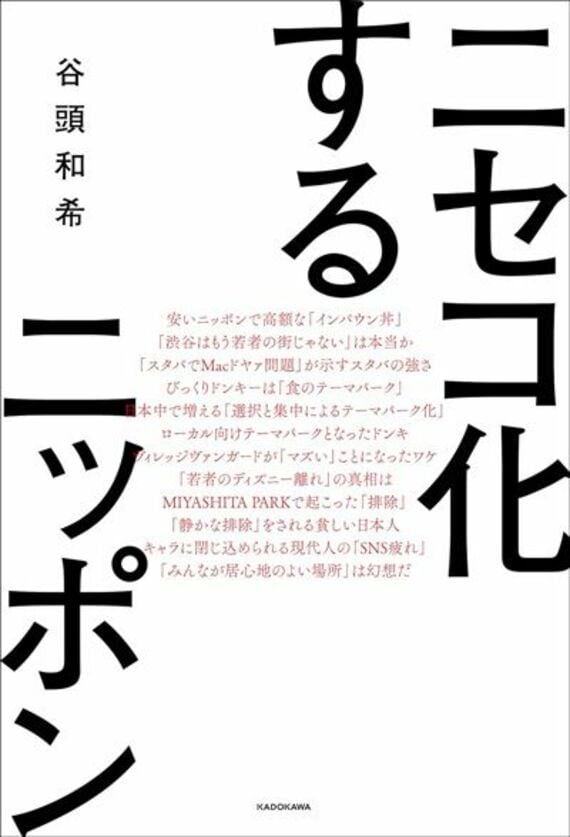






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら