「課金しないとどうなるかな」→「バカだった…」と激しく後悔 ジャングリアに「ファストパスなし」で参加した男の哀れな末路
財務状況も健全であり、2024年には東京ディズニーシーに新エリア・ファンタジースプリングスをオープン。さらに、2027年には東京ディズニーランドの主要アトラクションだったスペース・マウンテンとその周辺がリニューアルオープンする予定で、新規設備の投資が活発に行われている。

ジャングリアでも、当初は運営の不備などから、その値段に対して多くの不満がSNSやネット記事などで噴出した。そのとき、マーケッター界隈では「その値段に文句を言うような貧乏人はジャングリアのターゲットからは外れているから、なにも問題がない」という(少々過激な?)意見が出ていた。
ジャングリアのそもそものコンセプトは「Power Vacance」であり、沖縄でしかできないリッチな体験をゲストにしてもらうことが狙いである。だから、そもそも課金など厭わない人々がターゲットにされている……ということである。

このような例を見ると、結局は「課金」のほうへ舵を切るのは、それぞれのパークの経営戦略なのであるし、ディズニーリゾートのようにそれがうまく進んでいる例もあるのだから、特に口を出す問題ではないのかもしれない。(筆者を含め)少なくない人が「お呼びではない人々」になってきているというのは、寂しいことではあるのだが……。
「期待値」コントロールができるか
ただ、懸念がないわけではない。ここでは、2つのポイントをあげよう。
1つ目は、課金を前提にすればするほど、顧客の「期待値」が上がりすぎる、という点だ。
課金無しでなんとなくパークに行くのと、課金をして楽しみにしてパークに行くのでは、その期待値は大きく異なる。顧客がよりシビアになるのだ。例えば、富士急ハイランドのプレミアムチケットの場合、15分ほどの待ち時間でも「課金チケット代払ったのに、結局待たされたよ」と言われてしまう可能性が、なくはない。普通に考えれば、通常は数時間の待ち時間が15分なのだったらかなり良いと思うのだが、課金したことによってハードルが上がり過ぎてしまって、結果的に満足度が下がってしまう結果にもなりかねない。

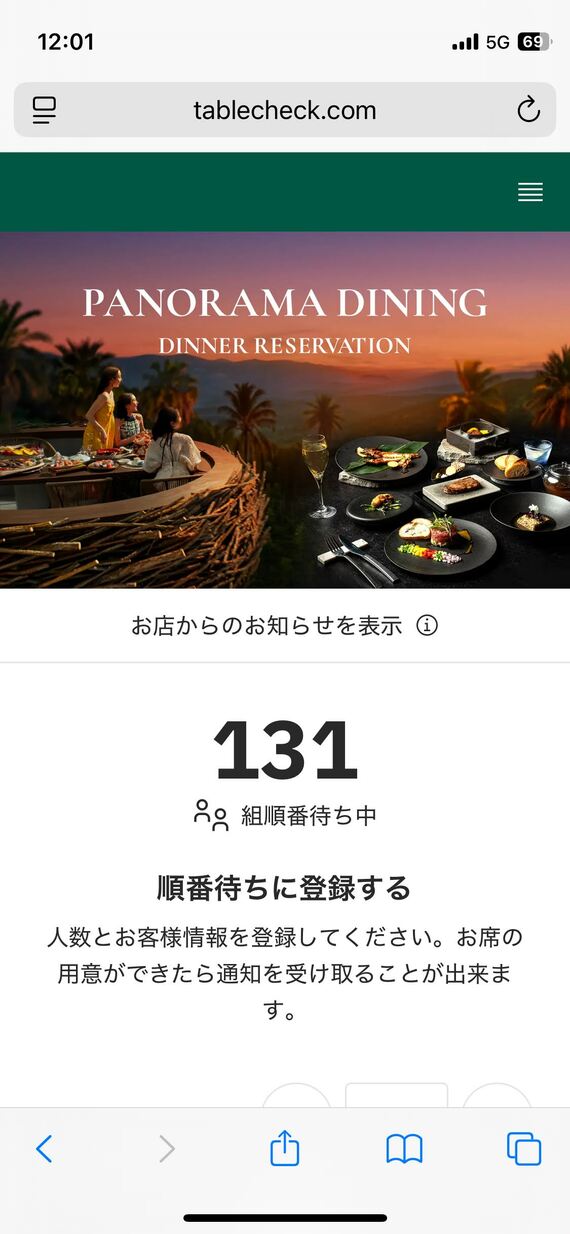































無料会員登録はこちら
ログインはこちら