バッタやカマキリに寄生して”脳を狂わす”「ハリガネムシ」の不気味で驚異的な能力とは?“食われる前提”で進化した生物たちの戦略
当然ながら捕食者に狙われる側は、必死に防衛しようとする。そして、捕食者は常にその上をいく。対策は巧妙なこともあれば力づくなこともあるが、動物が今日を生きのびようとすれば、絶対に必要なことだ。自分が餌を食べること、そして自分が餌にされないこと、これが絶対条件だからである。
……と書いてから気づいたが、しまった、食われるのが前提の動物もいた。
体内に入り込み、宿主を操る
最近わかったのは、ナナフシの卵だ。驚いたことに、ナナフシの卵は鳥の消化管を素通りして出てくる場合がある。植物の種子と同様、鳥に食われることでより広範囲に分散している可能性すらある。
鳥の中には発達した砂嚢(さのう・焼き鳥でいえば砂肝)で機械的に餌をすり潰すものもあるから、うっかり潰されて消化されてしまったら大変だが、飛翔能力の高くない(場合によっては翅はねが退化して飛べない)ナナフシにとって、鳥に運ばれるのは大事なチャンスでもあるのかもしれない。
もう一つ、食われる前提で生きているのは内部寄生生物だ。
ハリガネムシという実に奇妙な生物がいる。名前通り、針金のように細長い。そして、体が妙に硬くて、針金をペンチで曲げるようにクキ、クキと曲がりながら動く。ミミズのように柔軟にニョロニョロしないのである。
この生物はバッタやカマキリの消化管に寄生するが、幼生は水中生活である。これが水苔などと一緒にカゲロウの幼虫などに食われることで体内に入り込み、さらにその幼虫が羽化し、カマキリに食われることでカマキリの体内に移動する。
バッタに寄生する場合は、宿主の糞と一緒に休眠状態で排泄された幼体が、偶発的に草と一緒にバッタに食われることで移動するようだ。
ハリガネムシの驚異的な、そして不気味な能力は、この次の段階にやってくる。
ハリガネムシは交尾・産卵のために水中に戻らなくてはならない。そこで、彼らは特殊なタンパク質を生産し、宿主の脳に送り込む。この結果、どうやら宿主は水面の反射や偏光に走性(無条件にそちらに向かうこと)を示すようになり、自分で水に近づこうとする。最後には水に接触するか水に落ちてしまうのだが、その途端、ハリガネムシは宿主の体内から脱出し、水中生活に戻るのである。
こういう寄生生物の行動はいささか恐怖を覚えるものだが、食物連鎖の中で綱渡りしつつ、宿主を操って自分に都合のいい行動をさせる、という興味深いものでもある。
もっと言えば、病原体もこのたぐいだ。風邪を引くと咳やくしゃみが増えるが、あれは我々にとっては体内の異物を外に出す防衛反応である。だが同時に、ウィルスにとっては飛沫に乗って飛び、感染機会を増やすものでもあるのだ。
もちろん、ウィルスは何かを考えたりはしないだろうが(それどころか定義上、生物かどうかも怪しい)、効率よく増殖して自分のコピーを残すという意味で、適応的な行動をとってはいるのである。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

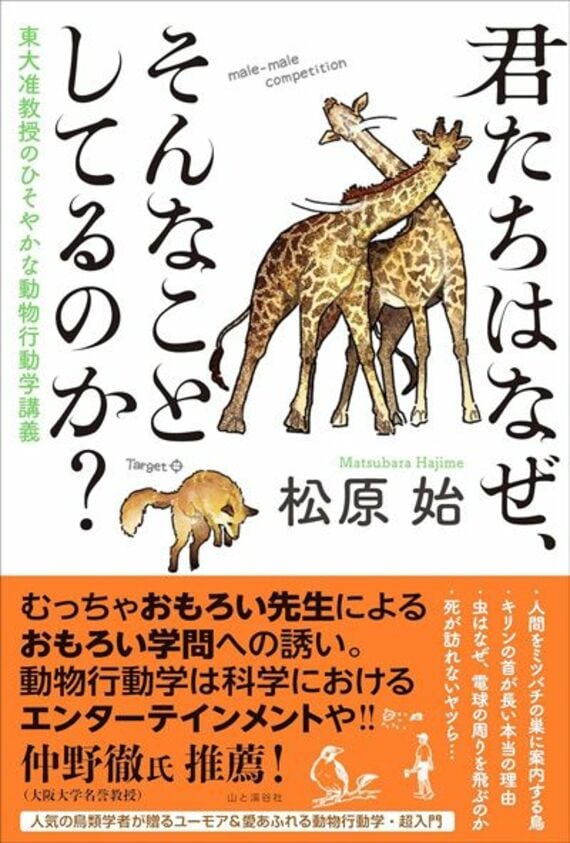






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら