ケース問題がいくら解けても「即戦力」になれない残酷な理由 あなたのその対策、コンサル実務では「50点」です
この「ケース問題」を解くために、志望者は対策本を読み込み、フレームワークを頭に叩き込み、模擬面接を繰り返しています。
「"売上向上"の問いには、まず売上を客数と客単価に分解して……」
「3C分析とバリューチェーンで構造化すれば、MECEな回答ができるはずだ」
そうやって思考の鎧を固め、面接官を唸らせ、内定を勝ち取れば、自分はコンサルタントとして華々しく活躍できるはずだ──。もし、あなたが本気でそう信じているなら、私はまず、その考えを一度リセットする必要がある、とお伝えしなければなりません。
なぜなら、その努力の方向性は、来るべき“本当の戦場”から見れば、あまりに無邪気な「ごっこ遊び」に過ぎないからです。
「ケース問題の勝者」が実務で通用しない理由
これは、長年コンサルティングの現場で新人育成に携わってきた私の、偽らざる実感です。拙著『問題解決思考問題』でも詳しく解説しましたが、ケース問題を使った試験を通過して内定を獲得できたからといって、入社直後から即戦力としてコンサルティングの実務で活躍できる人は滅多にいません。
理由は、極めてシンプルです。
そもそも面接のケース問題は、「短い時間で採用試験を実施するために内容が簡略化」されています。
しかし、私たちが日々対峙する現実の経営課題は、そんなに単純ではありません。最新技術の動向、複雑な社会情勢、クライアント企業の組織文化、そして人間関係。無数の変数が絡み合う混沌とした状況の中で、答えのない問いに挑むのが私たちの仕事です。
正直に申し上げて、実務で求められる思考の「広さ」も「深さ」も、面接のケース問題レベルでは「遠く及ばない」のです。
それは、いわば自転車の補助輪をつけたまま、きれいに舗装された公園を走っているようなもの。それでいくら速く走れても、本当の公道で、荒れた路面や予期せぬ障害物に対応できる力は身につきません。


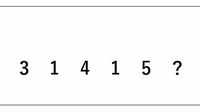





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら