それを知ったAさんは、少しでも長生きしてほしいとの思いから、「なんとかして治療を続ける道はないのか」と主治医に会って聞こうとしましたが、またもや思いとどまってしまったとのこと。
「自分がしゃしゃり出ていくことで、医師と患者である母との関係性が崩れてしまうかもしれない。医師が気分を害してしまったら、被害を受けるのは母親――そんな心配がよぎったんです」と、Aさんは言います。
母親が最期を迎えたのは、それから間もなくのことでした。
筆者は母親の看取りに関わりましたが、Aさんはそのときも「以前から調子が悪いというのを聞いていたのに、なぜすぐに検査を受けさせなかったんだろう」「母に代わって、私が医師に聞けばよかった」「治療をやめたときも、聞きにいけばよかった」「もっとできることがあったはずなのに……」などと、後悔の言葉が次々と口をついて出ていました。
大腸がんは、早期では症状がないことがほとんどです。ですから、お腹が痛いと訴えていた母親の病状から推測する限り、たとえ最初の段階で検査を受けていたとしても、早期ではなかった可能性は十分にあります。
しかし、「あのとき、もっと自分ができることがあったはず」と話すAさんの心の傷はとても深く、涙ながらに「この後悔は一生残ると思う」と語っていた姿は、今も目に焼き付いています。
もっとできることはなかっただろうか
大切な人を看取ったあとに「もっとできることはなかっただろうか」「あのとき、こうしてあげたらよかった」といった後悔は、多かれ少なかれ誰しもに残るものです。
実際のところ、後悔をゼロにするのは難しいですし、そもそもゼロにはならないと筆者は考えています。
ただ、これまで多くの患者さんの看取りに関わってきた経験から、残された家族が後悔を最小限に抑えるためのヒントはいくつかあるように感じます。ではそのヒントとは、どのようなものでしょうか。
まずは、判断に迷う状況があったら、後悔しないかどうかを、その時点で立ち止まって考えてみることです。


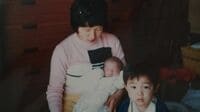




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら