常磐線の運行本数が「取手で半減」する複雑な事情 地磁気観測所と鉄道電化の長い「攻防」の歴史
ちなみに常磐新線(つくばエクスプレス)がこのころ着工したが、都心寄りが直流、規制圏の筑波寄りは交流で整備された。関東鉄道は1994年、常総線の電化について直流で305億円、交流では240億円かかるとの試算を提示。沿線開発や関係機関の協力がないと電化は困難との認識を示しており、これも事実上断念されている。
しかし、常磐線の直流化を求める声はいまもくすぶっている。たとえば茨城県が2024年6月にまとめた国への要望事項では、地磁気観測所の早期の県外移転が盛り込まれている。
実際のところ、地磁気観測所の移転と常磐線の直流化はどのくらいの費用がかかるのか。地磁気観測所に関しては、1995年5月27日付『朝日新聞』東京地方版(茨城)が「35億円とも50億円ともいわれる移転費用」と報じている。

直流化にいくらかかる?
交流電化されていた滋賀・福井県の北陸本線・長浜―敦賀間と湖西線・永原―近江塩津間(合計51.7km)を直流化したプロジェクト(2006年完成)では、車両費を含む総事業費が161億3400万円。1kmあたりでは約3億1200万円だった。これを単純に常磐線の取手―土浦間26.4kmに当てはめると約82億3700万円。移転費と合計すると最大で132億円程度だ。
ただ、北陸本線・湖西線と常磐線では列車の本数と必要な車両数が違いすぎるし、現在の物価水準を考えると132億円で済むとはとても思えない。それに地磁気観測所の柿岡への移転では当時の東京市が費用を一部負担しており、北陸本線・湖西線の直流化でも総事業費の9割近くを滋賀県と福井県が負担している。茨城県はどこまで負担できるだろうか。
あるいは、最終的な目的は直流化ではなく列車の増発だから、直流電車と交直両用電車のコスト差を国が補償するといったことも考えられる。実際、茨城県も同様の考え方を国への要望事項として盛り込んでいる。今後もこの問題は折に触れて浮上するだろうが、何かいい知恵が出てくればと思う。

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら













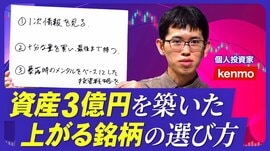


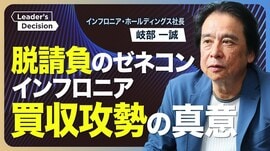




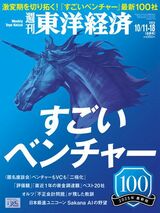









無料会員登録はこちら
ログインはこちら