常磐線の運行本数が「取手で半減」する複雑な事情 地磁気観測所と鉄道電化の長い「攻防」の歴史
結局、地磁気観測所から半径30km程度の範囲では鉄道の電化を規制するという国の方針が1928年末までに事実上固まったようだ。周辺で計画された電鉄は非電化の蒸気鉄道として開業したものや、観測への影響が小さい低電圧で開業したものもあるが、筑波高速度電気鉄道は計画自体が消滅した(この経緯は2019年11月22日付記事『上野発着狙っていた「幻のつくばエクスプレス」』を参照)。地磁気観測所は現在、電車による観測への影響が35km程度まで及ぶとしている。
一方で国鉄の常磐線は1936年に松戸まで電化。戦後の1949年には電化区間が取手駅まで延伸された。ここまでは電化規制の圏外だったが、国鉄はさらに電化の拡大を計画。地磁気観測所からの距離は土浦駅が約18km、石岡駅が約9kmで規制圏に入る。地磁気観測所と鉄道電化の問題が再燃した。

「交流電化」で問題回避
運輸省は1951年に小委員会を設置して技術的な検討を開始。1952年春から1953年春にかけ、東武鉄道と我孫子付近の既電化区間で電車による磁場撹乱の実測を行っている。1953年には運輸省や国鉄、中央気象台などによる協議会が設置され、調査と協議が本格化。常磐線の既電化区間で試験を実施し、1956年2月に「国鉄が採用している直流方式の電化は不可能」「交流方式の電化なら可能」と結論付けた。
当時の日本の電化路線は直流方式だけだったが、国鉄が1953年ごろから交流方式の電化を研究していた。交流は送電ロスが少ないなどの利点に加え、地磁気観測への影響も小さい。こうして1961年に取手以北が交流電化。取手駅から次の藤代駅までのあいだに直流と交流の境界になる無電区間(デッドセクション)を設け、ここで電車の回路を切り替えるようにした。













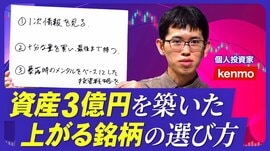


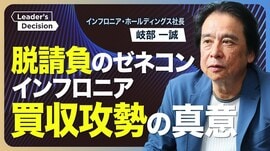




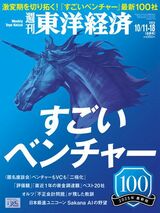









無料会員登録はこちら
ログインはこちら