常磐線の運行本数が「取手で半減」する複雑な事情 地磁気観測所と鉄道電化の長い「攻防」の歴史
地磁気観測の歴史は古い。日本初の本格的な鉄道が開業してから11年後の1883年、現在の東京都港区赤坂に臨時観測所が設置されている。1887年ごろには、江戸城旧本丸北桔橋門にあった中央気象台(現在の気象庁)構内での観測が始まった。
しかし1903年、東京で路面電車が開業。1904年には甲武鉄道(現在の中央本線)が電車の運転を開始する。このころから地磁気観測の「人工撹乱」が報告されるようになった。
電車が使う電気は変電所から架線を経て電車に入り、モーターを回してレールに流れる。このとき電流の一部が「漏れ電流」として地面にも流れるが、これが雑音になって地磁気をかき乱し、観測を困難にするのだ。
このため、東京市電気局(現在の東京都交通局)が観測施設の近くを通る路面電車を計画したのを機に移転が決定。中央気象台は「将来電車などが通りそうもない所がよい」(地磁気観測所編『地磁気観測百年史』1983年3月)として茨城県の柿岡町(現在の石岡市柿岡)を移転先に選び、明治から大正に変わった1912年、地磁気観測所が完成した。

茨城でも「電鉄計画」で再び問題に
ところが大正末期、周辺で私鉄の電鉄路線が計画されるようになる。昭和初期の1928年には、鉄道省(のちの運輸省、現在の国土交通省)が東京と筑波山を結ぶ筑波高速度電気鉄道の営業計画を許可。中央気象台は鉄道省に抗議するが、民間団体の関東商工会議所連合会は電鉄の整備に支障が生じるとして地磁気観測所の移転を要望し、問題化した。
中央気象台の第5代台長を務めた気象学者の藤原咲平は、のちに「茨城県では初めは土地の繁栄の意味で(地磁気観測所の柿岡への移転を)歓迎せられましたが、今では茨城県の交通の妨害をするといふやうな意味で地方の名誉職の方や県会議員といふやうな方が頻りと気象台を攻撃されて居ります」(『気象と人生』鉄塔書院、1930年)と語っている。茨城の「心変わり」に困惑していたようだ。













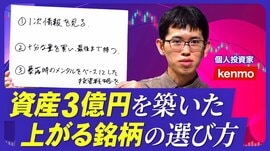


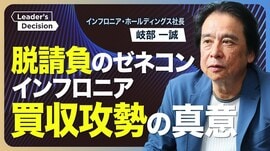




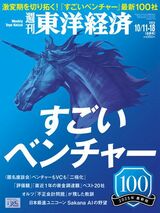









無料会員登録はこちら
ログインはこちら