常磐線の運行本数が「取手で半減」する複雑な事情 地磁気観測所と鉄道電化の長い「攻防」の歴史
これに先立つ1982年2月ごろ、関東鉄道が常総線の取手―水海道間を直流電化する計画を気象庁に打診している。この区間は東京の通勤圏で1977年から複線化が進んでいたが、水海道駅付近が直流電化規制圏のため電化できずにいた。
関東鉄道が示した計画は内房線と同じ特殊な方式で、変電所の設置間隔を短くして架線とレールを細かく分割。地磁気観測への影響は従来の直流電車の4分の1に低減できるとした。常総線と常磐線は地磁気観測所からの距離など条件が異なり一緒くたにできないが、気象庁の考えが変化した背景には関東鉄道が打診してきた計画があったのかもしれない。
地磁気観測所は1982年11月8~12日の深夜、特殊な方式による直流電化を想定した試験を常総線の沿線地域で実施。取手―水海道間を直流電化しても地磁気観測に影響を及ぼさないことを確認している。続いて1983年の1月から2月にかけては、地磁気観測所問題研究会の専門部会として、常磐線の既電化区間で直流電車の実測試験を実施した。

一部機能の移転案は実現せず
こうして検討が進んだ結果、地磁気観測所の一部機能移転案が浮上する。観測所では地磁気の変化を長周期と短周期で観測しているが、このうち短周期観測は移転可能とし、これにより直流電化規制圏を半径18kmまで縮小できるとした。これなら常磐線は取手止まりの直流電車を土浦まで延長でき、常総線も特殊な方式によらず直流電化できる。
しかし、この案が実行に移されることはなく、1994年ごろに事実上断念されている。一部といっても移転費用がかかるし、さらに取手―土浦間を直流方式で電化しなおすための費用もかかる。これを誰がどう負担するか、解決できなかった。













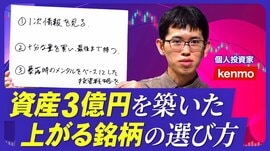


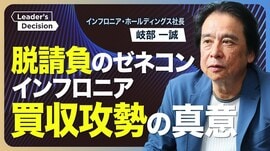




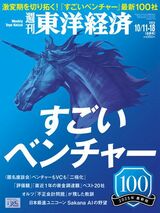









無料会員登録はこちら
ログインはこちら