常磐線の運行本数が「取手で半減」する複雑な事情 地磁気観測所と鉄道電化の長い「攻防」の歴史
ちなみにこのころ、国土地理院の地磁気観測施設である鹿野山測地観測所(千葉県君津市)でも、近くを通る房総西線(現在の内房線)の電化計画が問題になった。こちらは直流方式で電化しつつ、変電所の間隔を通常より短くして架線・レールを電気的に分離。これにより漏れ電流を減らした。測地観測所も一部の観測業務を岩手県水沢市(現在の奥州市)に移転して対応している。
交流電化により常磐線の電化問題は一件落着……のはずだったが、1981年ごろにまたしても問題化する。茨城県などが地磁気観測所の移転による常磐線の直流化を要望したのだ。
「直流化」で列車増発へ移転要望
常磐線では東京都心から取手まで直流電車が大量投入され、高頻度運行されている。一方、直流電化規制圏の土浦方面に直通する列車は直流と交流の両方に対応した電車を使用しているが、交直両用電車は構造が複雑でコストが高い。そのため大量には導入できず、運行本数も抑えられてしまう。そこで茨城県などは、地磁気観測所が移転すれば直流電車が乗り入れ可能になり、列車が増えると考えた。

これに対して気象庁は難色を示す。この時点で柿岡での観測開始から70年近くが過ぎており、同一地点での観測結果の連続性も重要になっていた。ここへきて移転すれば、せっかく蓄積してきた観測データが無駄になりかねない。
ところが気象庁は1982年8月に「地磁気観測所と地域開発が共存しうる道、あるいはその制約条件などについて検討を加える用意がある」と表明する。9月には茨城県や運輸省、気象庁、地磁気観測所、国鉄などで構成される地磁気観測所問題研究会が発足。技術的検討が本格化した。













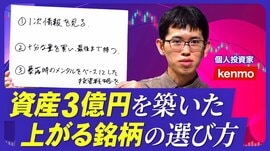


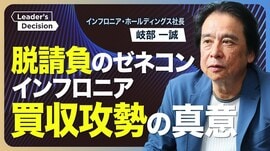




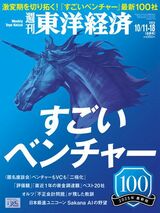









無料会員登録はこちら
ログインはこちら