トランプによるウクライナ戦争の停戦交渉はなぜ失敗するのか、古典が示す世界で戦争が絶えない根本的な理由
悲観的な見解になるのだが、「いまひとつの結論は、共通の基準をすべての国家に守らせることは難しいということである」(307ページ)。国家に道義を求めることは無理だという。また国家は、道義を破っても個々人のように逮捕され処罰を受けるわけでもない。
国家の持つ力のリアリズム
要するに、国家と国家が対峙する世界では、国家を制御することが難しいということである。もちろん、戦後巨大な超国家となったアメリカのような国家が無理矢理に上から押さえつければ、弱小国家はひれ伏すしかない。戦争裁判のように弱小国家は罰を受けるのである。しかし、今のアメリカにその力を求めることはできない。
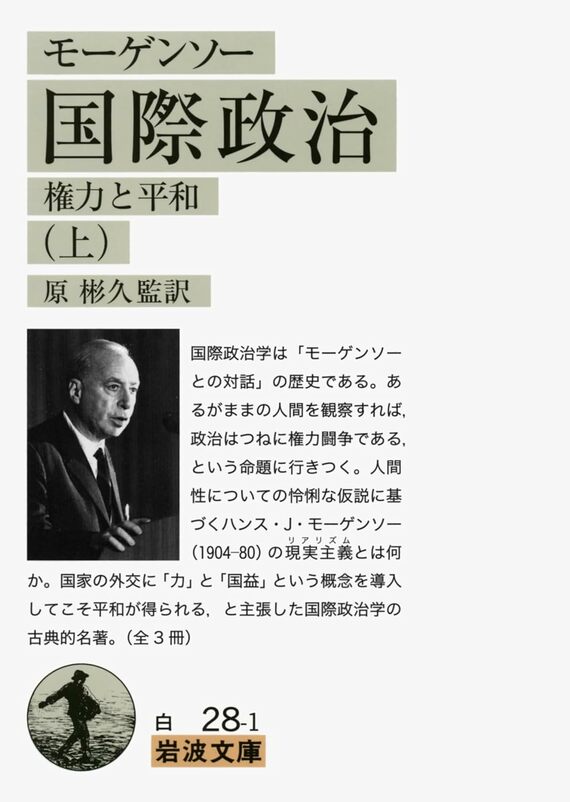
戦後巨大化したアメリカによる国際的機関や法律が施行されていく中で、これに対して悲観的に見ていたのがシカゴ大学のモーゲンソーである。この書物が出版された1948年は、米ソ対立が深まり国際社会が2つの陣営に分かれて世界国家という戦後のユーフォリアを吹き飛ばしたときであった。
現実が理想を壊していった時代であったといえる。リアルな現実は国家間、東西陣営間の対立の世界であり、国際社会を1つにまとめる時代ではなくなりつつあったのだ。
1940年代から1950年代にかけて外交官としてアメリカの外交政策に深く関与したジョージ・ケナン(1904~2005年)が、ソ連を「討論不能の相手だ」と決めつけ、力と力との対決へと進んだ時代である。
モーゲンソーはずばりこう述べる。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら