このため坂内では、「候補地の競合店を食べに行く」「現地の日本人ではない人のコメントを聞いてマーケティングする」ことを大切にしている。
この「日本人ではない」というのもポイントだ。一般的に、日本企業が海外進出すると、現地の日本人や、日本人が多く働く企業と商売をしがちだ。「日本の駐在員をターゲットにしている」と明言する飲食企業もある。
しかし、坂内はそうしない。なぜなら、日本人は世界でも突出してグルメな民族だからだ。「おいしいものをわかっている自分でいたい」という意識も強く、食が自己表現の一環にもなっている。
とても良いことなのだが海外出店においては、チェーン店というだけで避けられたり、「日本と違う」などと言われる場合も多いそうだ。それは坂内にとってプラスにならないばかりか、過小評価につながってしまう危険性もはらんでいる。

隠れた市場指標「アジア系スーパー」
中原社長はさらに、興味深い出店エリアの選定基準を教えてくれた。それは「アジア系スーパーがある地域」を重視するという独自の指標だ。「なぜかというと、スーパーの品揃えには、近隣に住んでいる人の嗜好が反映されているからなんです」と中原社長はいう。
少し噛み砕くと、アジア系スーパーのあるエリアには、アジア人もだが、欧米人でも、タイ料理や日本料理が好きな人、すなわち「アジア料理への偏差値」が比較的高い人が多く住んでいる場合が多いそうだ。だから、オープンした際の立ち上がりがいいのだという。
アジア料理=日本の料理とは異なると思う人がいるかもしれないが、アジアの料理は時を経て混ざっていくのが特徴。ラーメンも、元々は中華料理だ。それに、アメリカの一般消費者からしたら、日本、韓国、ベトナム料理の違いをわからないことも多い。
事実、アメリカのアジア系スーパー、飲食店の商品やメニューもさまざまな国が混ざっている。日本料理店ながら、生春巻やチゲを提供する店もある。「アジア料理」の雰囲気やイメージを好む人が多いので、国を明確に線引する必要はないそうだ。
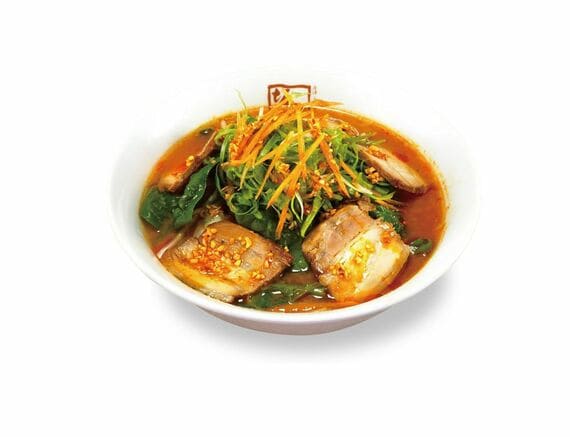
フランクフルト選定の決め手は「中央値」
と、ここまではラーメン店がどんどん増えているアメリカの話だが、2025年2月、坂内がヨーロッパ初出店を果たしたドイツは、また違ったフェーズにいる。
ドイツも、「アジア人が比較的多い」フランクフルトに出店してはいる。ただしこちらは、ドイツ単体ではなくEU全体で考え、「物理的にも物価的にも、食文化への融合性も中央値だから」選んだのだそうだ。日本で静岡から新業態をはじめるチェーンが多いように、「本格進出を占う」マーケティングにちょうどいいと考えたのだ。

加えてフランクフルトは世界的な金融都市で、「日本食自体の偏差値が高い層」や「食の冒険を楽しむ層」が厚い。また、タイ料理や寿司店はすでに浸透しているが、ラーメン専門店はまだ「新鮮さ」を保てる数軒で、それらのレベルは非常に高かった。
「こういった店の味を理解できるのであれば、我々もやれるだろうと判断しました」と中原社長は決断を振り返る。
最初はデュッセルドルフも候補に上がっていたという。だが、デュッセルドルフは日本文化がかなり浸透していて、「リトルトーキョー」のようなエリアもある街。競合が多すぎた。
そこから少しずつ離れて探したところ、フランクフルトは競合が少なく、前述した複合的な面から「これから偏差値が上がってきそうなブルーオーシャン」だと判断したという。
実際出店したところ、「よくきてくれた」「こんなラーメンを求めていた」という声が多くあったそうだ。客層は、金融系の企業が多い立地もあって、スマートなビジネスマンが中心だ。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら