「指示待ち部下」はAIに取って代わられる…!? これからの時代を生き抜くために“自分で考える力”を鍛える《数学脳》とは?
このように、図を描くことで、すでに分かっていること(かけ算九九)をもとに3×12という新しい問題を解くことができるようになります。また、3×12は、「3×3と3×9」、「3×4と3×8」、「3×5と3×7」と分けることもできます。
3×12=36という答えにたどり着く方法は様々です。自分の頭で考える人は、1つの問題に対し自由に発想することができるのです。
AI時代の今、自分の頭で考える人になろう!
以上、かけ算について説明しましたが、いかがでしたでしょうか?
3×5という小学校で習う数式でも、自分の頭で考えることで、数式の背後に広がる世界が見えてくることを実感していただけたかと思います。
このように、自分の頭で考えることを支える力が数学脳です。数学脳は、数学という学問を創った人の考え方と言っても過言ではありません。AIを含め科学技術を支えているのは数学です。数学脳が身につくと、科学を俯瞰する方法を身につけることもできるのです。
数学を支える数学脳は、AI時代にクリエイティブに活躍するための強力な武器となります!
これまで、私たちは、試験で効率よく点数をとるために、つめ込み型の勉強をしてきました。同様に企業も効率を重視し、上司の指示どおりに働く人材を育ててきました。
かけ算九九を覚えるだけでは、かけ算の背後に広がる世界が見えないように、上司の指示どおりに働くだけでは、ビジネスを広く、柔軟に考えることが難しくなります。AI時代に突入する今こそ、数学脳を鍛え、自分の頭で考える人になることが急務です。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

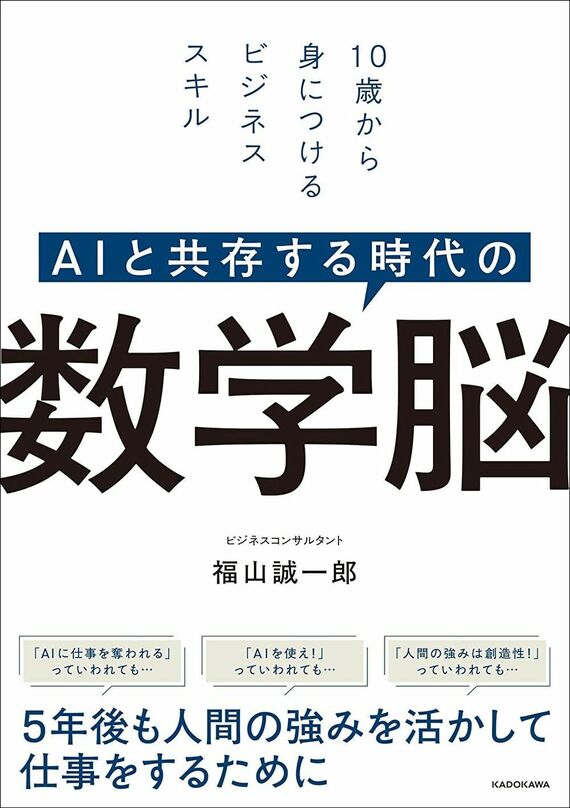


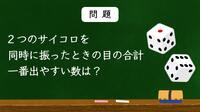



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら