――系統用蓄電池の開発を10年来進めてきました。このビジネスに期待することとは。
系統用蓄電池は徐々に新規参入が増え、売電価格は少しずつ下がっていくだろう。われわれは先行者利益で(機動的に動き、確実に収益を得る)「ヒットエンドラン」を狙っていく。
北海道千歳市ではすでに6000キロワットの「蓄電所」を展開しているが、これから建設に入るものを含めて全国で10万キロワットの蓄電所を立ち上げる計画だ。これらでは10%近い利回りを確保でき、年間数十億円の利益が得られるとみている。
ただ再エネはプロジェクト期間が非常に長い。長くしないと投資回収が進まない。売却を含め、イグジットの仕方は工夫していく。脱炭素案件は投下資本も積み増していくことになる。
それに見合った収益を上げていきたいが、長期的なインフラプロジェクトが中心なので、収益貢献は2030年以降になる。
その間はやはり、ガスや電力のトレードを中心に足元の利益を積み上げていきたい。
――洋上風力発電など再エネ案件の収益化は国内問わず容易ではありません。
われわれがやろうとしているのは、相応の持ち分の下でプロジェクトの主体として開発を主導し、ある程度開発が進んだ段階で持ち分の一部をプレミアムを乗せて売却して利益を上げていく、という手法だ。
完工した後は運転をしながら、残りの部分を回収していく。それでプロジェクト全体の利回りを上げていく。以前はあまりそういうことを考えずにやっていたが、最近はきちんと考えていかないと、社内のハードルレートを超えることができない。
――収益化に時間のかかる脱炭素案件では、予算を立てたり収益管理をするのが難しそうです。
蓄電池や再生可能エネルギーはすでにビジネスとして立ち上がっているから、予算を立てて実施し、進捗度に応じて収益を評価できる。
一方、今の時点では費用が先行して計上されていくバイオマス発電や水素、アンモニア、CCSといった事業は育成事業として位置付け、黒字化の目標年度を設定しながら進捗を定性評価していくことになる。
再エネの「事業承継問題」に商機
――需要家の開拓はどう進めていきますか。
「自分たちの電源構成の中で、少しでもグリーン電力を増やしたい」という思いは顧客にも共通している。エネルギー業界のみならず、化学業界や自動車業界の方々にも当社のネットワークを通じて売りに行く。
例えば長崎県西海市江島沖の洋上風力は2029年8月から電力供給を開始する予定で、プレミアムを払って買ってもらえるたくさんの顧客と話ができている。ここは強みかなと思う。
顧客も2030年以降のグリーン電力の需給がどうなっているかを考えている。再エネの適地は限られる一方で、再エネ電力の需要は高まっていく。大量の電力を消費するデータセンターも増加している。そうすると、今は多少高くとも、ある程度再エネ電力を押さえておきたいという心理が働く。プレミアムといっても、単位あたり数円程度だが。
再エネ事業では、すでにかなりの事業者が廃業していく可能性が懸念されている。せっかく増えた再エネが継続されない恐れがある。ここにまた、別のビジネスチャンスが出てくる。われわれが代わりに事業を引き継ぎ、お客さんときちんとつなぐようなビジネスが出てくるだろう。
(聞き手:森 創一郎)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


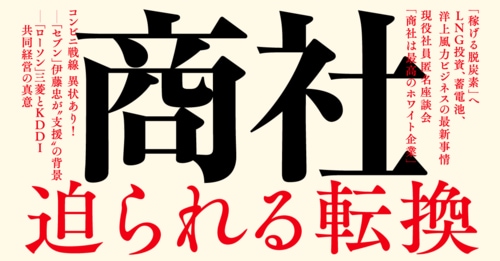































無料会員登録はこちら
ログインはこちら