浮体式の発電コストは従来の着床式の2倍以上。どう稼ぐのか。

日本政府は再生可能エネルギー普及の“柱”として、洋上風力発電の拡大を図る。目標は2040年までに3000万〜4500万キロワットの発電容量を導入すること。その商用化は、2023年1月に秋田県秋田港、同能代港湾内で始まったばかり。
この秋田の洋上風力を手がけるのが丸紅だ。港の岸壁からは、巨大な風車が海上に整然と並ぶ姿を眺めることができる。ただ同社が設置した「着床式」の風車による発電容量は2エリア合計で14万キロワットと少ない。
着床式に適した海域は少ない
日本全体で見ても、着床式の導入に適した遠浅の海域は少なく、この方式での発電容量拡大には限界がある。そこで着床式からの移行が期待されるのが「浮体式」だ。
海底に風車の基礎を固定する着床式と違い、風車は海に浮かぶ構造物の上に設置されるため、水深の大きい海でも導入可能だ。風車の収益性を左右する風況は一般的に、岸から離れるほどいい。
この浮体式でも、丸紅は他社に先んじて実績を重ねている。

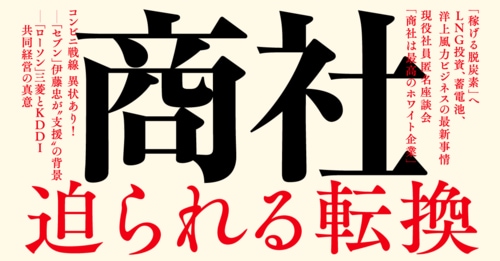































無料会員登録はこちら
ログインはこちら