「姫宮のご病状は、格別どうということもありません。ただこの幾月か、お弱りになって、きちんとお食事などもなさらないことが続いたせいか、このようなご様子なのです」と光君は言う。「見苦しいお席ですが」と、御帳台(みちょうだい)の前に敷物を敷いて案内する。姫宮も、女房たちがあれこれ身繕いをさせて、御帳台の下におろす。院は几帳を少し押しやって、
「夜通し加持祈禱をする僧みたいな気分だけれど、私はまだ験力が身につくほどの修行も積んでいないから、決まり悪いが、あなたが会いたいとお思いの私の姿をよくご覧になるがいい」と言って涙を拭う。姫宮も、ひどく弱々しく泣いて、「とても生きていけそうにありませんから、こうしていらっしゃったついでに私を尼にしてください」と言う。
「本当にそうお望みならまことに尊いことだが、そうは言っても、これであなたの寿命が尽きたとは限らない。もしこのたび生き長らえたとしたら、先の長い若い人は、出家後にかえって間違いが起きたり、世間の非難を招くようなこともありがちだから」と院は言い、光君に、「こうして自分から言っているが、これで最期だというのなら、ほんのいっときにせよ、その功徳があるようにしてやりたいと思う」と言う。
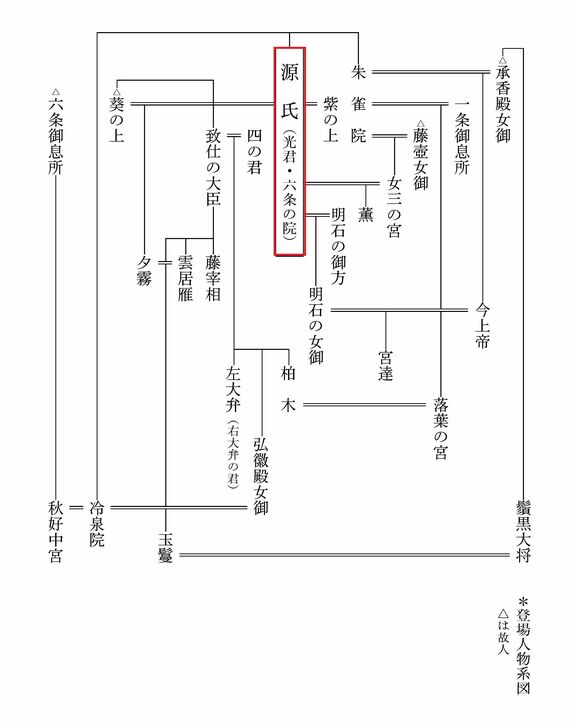
尼の暮らしであっても安心できるように
「この何日かそのようにおっしゃっていますが、物の怪などが取り憑いて人の心をたぶらかし、こうした考えを起こさせることもありますから、と申しあげて、取り合わないようにしています」と光君。
「物の怪が言わせているとして、それに従ったからといって、悪い結果になるのであれば差し控えもしようが、こんなに衰弱した人がもう最期かもしれないと望むことを聞き流すのは、後々、後悔に苦しみそうだ」
朱雀院は心の内では思うのである。これ以上ないほど安心だと思って姫宮を預け、光君もそれを承諾したのに、それほど愛情も深くはなく、期待していたようではない様子だということを、この何年も何かにつけて噂に聞いて心を痛めていた。しかしそれを表に出して恨むべきではない、そう思って、世間がどう想像してどんな噂を立てているのかも、ただ不本意に思い続けてきただけだ。この機会に姫宮が俗世を捨てても、もの笑いとなるような、夫婦仲を恨んでの出家とは思われないだろうし、それも悪くないかもしれない。愛情は薄くとも、姫宮の後見としては、光君のお気持ちは今後も充分頼ることができそうだし、やはり姫宮をお預けしたのは間違ってはいなかったと思うことにして、あてつけがましく光君に背を向けるのはやめよう。姫宮は、故桐壺院(きりつぼいん)の形見分けとして、広く趣ある邸を継いでいるから、それを手入れして住まわすこととしよう。私が生きているあいだは、尼の暮らしであっても安心できるようにしておきたい。それにこの光君も、そうはいってもよもや姫宮を粗略に扱い、見捨てることなどなかろう、そのお心を見届けようではないか──、と決意して、
「それならばこうしてやってきたついでに、せめて出家の戒をお受けになって、仏とのご縁を結ばれるのがよかろう」と院は言う。
次の話を読む:9月29日14時配信予定
*小見出しなどはWeb掲載のために加えたものです
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら