原動力は「選手強化」大規模アイスショーの舞台裏 フィギュアブームが追い風、「羽生結弦」の存在感
そもそもアイスショーという文化は欧米が先行し、日本では「フィギュアスケート=冬季五輪」というイメージでしか知られていない時代が長かった。「フィリップ・キャンデロロ ジャパンツアー2001」は、CICが自らの力で立つための第一歩であると同時に、日本にエンターテインメントとしてのフィギュアスケートを輸入する取り組みでもあった。
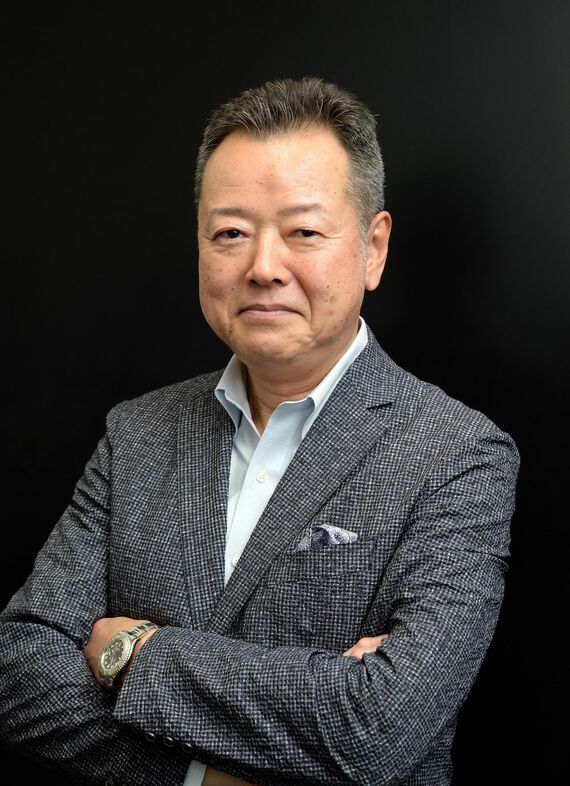
手探りの中で主催したこのショーは集客に苦戦し、2000万円の赤字となった。創業間もないCICにとっては非常に厳しい結果だったが、そこで諦めず開催した翌年の「フィリップ・キャンデロロ・ファンタジー・オン・アイス2002」では黒字を出せた。
翌2003年はまた大赤字になってしまい、その後「ファンタジー・オン・アイス」と銘打ったショーが復活するのは2010年のことだ。が、フィギュアブーム前夜、2000年代初期に主催したこの一連のアイスショーの経験がCICの方向性を決めたという。
「当初は、ビジネスを軌道に乗せるため、自社の看板商品をつくるため必死でした。ところが最初の年、2001年のショーが終わった後、日本スケート連盟から『選手にとって貴重な経験になった』とお礼を言われたんです」(真壁社長)
「感謝されたら、もう続けるしかない」
フィギュアスケートがマイナー競技だった時代の日本では、トップ選手でも大勢の人の前で演技をする機会は少なかった。日本の選手にとって、不慣れな環境で行われる試合は心細さや緊張と戦う場でもあっただろう。
一方、アイスショーの盛んな国や地域の選手には、観客の反応を見ながら演技をしてきた経験がある。競技においても、ショーで培われた表現力、ジャッジや観客へのアピールなどの面で、大きな差が出てくる。この差を埋めるのにCIC主催のアイスショーが一役買うこととなった。
また、日本がフィギュアスケート強国になる前は、海外のトップスケーターや一流の振付師との接点を持とうにも、国際大会の場くらいしか機会がなかった。トップ選手はどのような練習メニューをこなし、どんなふうに滑り、どう跳ぶのか。それを間近に学べるアイスショーは、本番だけでなく事前の練習も含めてよい刺激になる。
民間企業のCICが、海外のスターを招き日本で開催したショーは、図らずも日本の選手に観客の前で演技をする機会、世界レベルのスケートに触れる機会を提供したのだ。ショーには、後に五輪で日本代表として活躍することになるスケーターも出演していた。
「社業発展のために企画したショーでしたが、選手の強化につながると感謝されてしまったら、もう続けるしかない。うれしかったんです。1年目に大赤字を出しながら、2年目に再び主催したのは、日本のフィギュアスケートが強くなっていくために何かできることがあるなら、という思いからでした。その思いは今も変わりません」(真壁社長)































無料会員登録はこちら
ログインはこちら