「頭の回転の速い子」が数学で得たスゴい思考の型 算数・数学の「頭の使い方」は日常生活に使える
こんな感じですね。さて、ここまで考えた上で、数学ができる人は、「これらの要因を置き換えると、どうなるだろう?」と考えます。先ほどの数学の置き換えの要領で、これらの要因を文字で置き換えるのです。
例えば、「料理を作るのに時間がかかる」「注文が抜けてしまう場合がある」は厨房での料理スピードの問題ですね。これをAとおきます。
「注文を厨房に伝えるのが遅い」「厨房に伝達ミス」は厨房に注文を届けるまでの問題ですね。これをBとおきます。「届けるまでが時間がかかる」は厨房から料理を届けるまでの問題ですので、これをCとおきます。これをまとめて、置き換えて数式を作ると、
=A(料理を作る時間)+B(注文伝達の時間)+C(料理を届けるまでの時間)
と考えることができます。
置き換えると「思考のモヤモヤ」が晴れる
数学ができる人は、パッと頭の中にこの数式を思い浮かべることができるのです。
これができれば、「じゃあ、提供スピードを改善するには、このA〜Cの要因のうち、まずはAを解決するために動こう」なんて具合に思考を進めていくことができます。こうすれば思考のスピードも速くなりますよね。
数学には、モヤモヤしたわけのわからないものを定義して置き換えることで、考えやすくする機能があると言えるのではないでしょうか。
いかがでしょうか?
僕も昔は「数学なんて勉強して何の意味があるの?」と考えていた時期もありました。
しかしこうやって考えてみると、数学には無限の意味があると思います。みなさんもぜひ、参考にしてみてください。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


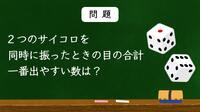
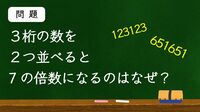
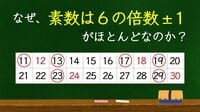



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら