死の現場を支える「葬送の仕事師」の正体 すべては「不在の在」を演出するために
ある火葬場職員はこう語る。
「直葬も引き取り手のない方も、ここで僕らが心を込めて火葬したら、ちゃんと送れると思うので」
このような一人ひとりのプロの手によって、モノトーンの彩り、サイレントの響き、平穏の造形が構成されていく。すべては葬儀というパーソナルなイベントにおいて、「不在の在」を演出するために。
別れの時間を尊ぶ想いが、技術の進化に
中でも、近年特に注目を集めているのが、エンバーミングと呼ばれる技術である。動脈に衛生保全液を注入し、静脈から血液を排出することにより、遺体の腐敗を遅らせることが出来るものだ。さらに、損傷した顔のパーツを元通りに修復処置をするなど、生きていたときの姿に極めて近い容貌に甦らせることが可能であるという。
最大の効能は、別れの時間をコントロールできることにある。極端な例をあげると、エンバーミングした遺体は、自宅に50日間寝かせておくことも可能なのだ。本書では、この技術を活用しエンバーミング後の遺体とともにドライブを行った30代の女性の話なども紹介されている。エンバーミングの費用は、本書に登場する会社では約12万円。全国でまだ2%程度の普及率というが、これから増えてくることが確実視されている。
このような光景の裏側で、技術の進化と慣習の風化が同時に起こっていることは注目に値するだろう。遺体を扱う技術の進化、それが多様性を生み出し、葬送の市場を慣習の外側へと押し出しているのだ。
それが特殊なフィールドであったとしても、ビジネス世界の在り様は市場の変化を汲み取りながら変貌を遂げていく。例えば介護サービスの企業が葬送ビジネスに進出した等という話を聞くと、ビジネスにおける打ち手としての納得感と複雑な気持ちの双方が入り交じるだろう。業界の動向そのものが、生と死が地続きであることを指し示しているのである。
さらにこの変化は、今後、葬送業界がボーダーレスとなり、再編が加速することも示唆している。弔いの世界に商いの論理が押し寄せ、「結界」は変容を迫られているのだ。その中には、ファスト化や価格破壊といったものも含まれるかもしれない。だが心意気や職業倫理といったものは、変わらずに継承していって欲しい。著者が、葬送の仕事師たちの「心」の部分にフォーカスしている背景には、そんな願いが込められているような気がしてならない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

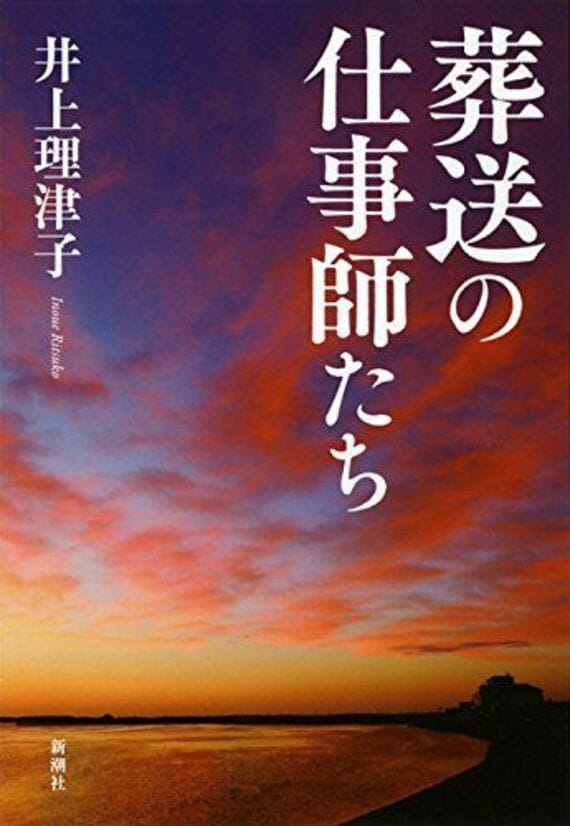






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら