「海外で売れまくる日本酒」を生み出した獺祭会長の“よそ者人生” 「地元で苦労したから外に出られた」と語る真意、そして事業承継への思い・・・

東京でつかむことができたチャンス
――先代の急逝に伴って経営を引き継いで40年、山奥の小さな酒蔵から今では大きく変貌を遂げました。最大の転機はどこにあったと振り返りますか。
いちばんは経営難ですよね。地元のどこでも勝てない、何とかしなきゃいけないという中で、東京市場を狙うしかないと出て行った。東京に行くと、旭富士(獺祭が生まれる前に製造していた銘柄)では相手にしてもらえない。
そんな中で(精米歩合が50%以下の)純米大吟醸にだんだん特化していった。純米大吟醸に特化しながら、データを活用することに気がつく。データを活用して省力化するのではなく、データを活用しながら人を使う作り方に踏み込んでいった。
そうこうするうちに社会が変わって、川上より川下のほうが強くなり、銘柄の選択権をお客さんが持ち始めると、そのマーケットに獺祭の純米大吟醸がばっちりはまった。









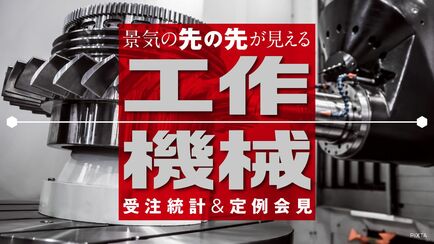






















無料会員登録はこちら
ログインはこちら