前出の『週刊サンケイ』の16万人は、ほかの団体を含めていないとはいえ、この記事を読むと4年程度で奨学生は倍近くに増えたようにも思えるが、同年の『オール讀物』(文藝春秋/1957年11月号)では「奨學金で勉強している學生は全部で22萬人」、『漫画読本ガイド』(文藝春秋/1958年3月号)でも「奨学生の総数は約22万」とあるので、育英会以外の団体で6万人もいたのだろうか。ただ、どの団体も毎月の支給額は、2000~3000円というのは変わらない。
1950年代・奨学金を借りる学生たちはヒドい言われようだった
ところで、この『週刊新潮』の記事は奨学生たちに対して辛辣で、育英会の庶務課長に「御本人たちは社会保障の一種だと割り切っていまして」と言わせ、地の文章では「昔のいわゆる苦学生を“バイト学生”に、また“上から恵まれる給費生”を“権利として受取る貸費生”に変ボウさせた(中略)終戦直後の経済的混乱期が日本人の頭をすっかり洗脳してしまったのかも知れない」と、奨学金を借りる学生にそこまで言わなくてもいいのではないか、という具合で罵っている。もし今、日本学生支援機構(JASSO)の関係者がこんなことを言えば、大炎上も間違いないだろう。
その後もアルバイトに明け暮れる貧乏学生の肩を持ったかと思えば、奨学金を借りる女子大生については「虚栄心から貧しいことを隠したがる心理傾向があること」「奨学資金をもらった女と結婚すると、借金を支払わされる」と、決めつけの強い物言いである。
その一方で、高度経済成長期前夜ということもあり、雅叙園の社長・松尾国三氏が私財を投じて作った育英会や、松下電器(現・パナソニック)や三井鉱山(現・日本コークス工業)など民間からの育英会と、その後の企業による引き抜き(記事ではヒモツキ奨学金と喩えている)などもしっかりと紹介。
それでも、最終的には「会社員という平均人間になりたがる若者が多い」世の中を憂えて、「英才を育てるはずの“育英資金”はいったいどういうことになるのだろう」と、嘆いている。会社員になることの何が悪いのか? そして、奨学金に夢を持ちすぎではないか? 現代を生きる人間としては、そう思わざるを得ない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


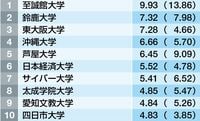































無料会員登録はこちら
ログインはこちら