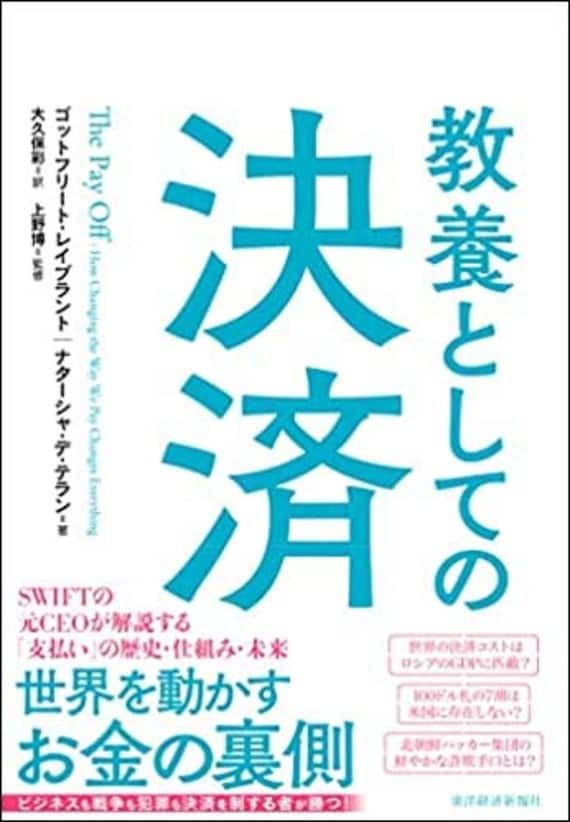ドラマ『ペーパー・ハウス』は時代錯誤
ネットフリックスの人気ドラマシリーズ『ペーパー・ハウス』では、「プロフェッサー」と よばれる首謀者が遠隔で指揮をとりながら、さまざまな分野に強みをもつ泥棒の集団が、スペインの王立造幣局──通称「カサ・デ・パペル」(「紙の家」という意味で、スペイン語版の原題にもなっている)──に侵入する。
泥棒たちは、警察が予想したようにたんに戦利品をつかんで逃げるのではなく、人質たちとともに立てこもり、印刷機(そしてこのドラマシリーズ)を動かし続ける。11日間そこにとどまり、追跡不可能な紙幣を24億ユーロ印刷することがかれらの目的なのだ。
この筋書きは独創的でドラマチックかもしれない。しかしその巧妙さとは裏腹に、この強盗は実にアナログなものだ。デジタル社会の現代において、「プロフェッサー」ほど創意にあふれる人物の手口とは思えない。決済の分野では、サイバー犯罪との戦いが以前から大きな課題となっているのだ。
画面上であれ実生活においてであれ、アナログ決済もデジタル決済も、盗難や詐欺のリスクをはらんでいる。なぜなら決済はお金の出入り口だからだ。