MMTが主流派経済学に代わるパラダイムである訳 「非常に良い事例」である日本から考える意義
私たちの常識にも根強く影響している主流派経済学があまりに非現実的な前提に基づいていることもあり、「政府に対する債権証書であることが、通貨の価値の裏付けである」というMMTの貨幣観は、現実の経済や経済政策を見る目を一新してくれます。それは、日本が財政危機ではないこと、そして長期停滞の原因である緊縮財政から脱却すべきであることを、明快に説明してくれます。
さらに、MMTの貨幣観は、主権国家のルーツを浮き彫りにすることで、緊縮財政に固執して経済政策や安全保障政策で迷走している今の日本政府が、「公益実現という政府本来の債務を履行する」という自らの役割を放棄することによって、財政破綻どころか己れの存在意義を自ら失わせていることを強く示唆しています。同時にそれは、何千年にもわたって人間社会にとって重要な存在であり続けてきた貨幣に対する見方を変えることで、経済学のみならず、(本書第2章でも述べているように)歴史学をはじめとする他の人文社会科学にも見直しを迫るものかもしれません。
経済学のパラダイム転換はまだまだ続く
一方で、現在のMMTの説明や主張がすべて正しいわけではなく、理論として改善・発展の余地があることも、本書の中で指摘したとおりです。本書では、経済の長期循環の観点から、ケインズが唱えた「投資の社会化」を「総需要のコントロール」という従来のケインズ経済学の枠組みを超えた政策論として定義し直し、MMT派が唱える就業保証プログラムよりも有意義な処方箋として提示しました。それは、まだMMTの存在すら知らなかった2015年の著書『積極財政宣言』で掲げた「ケインズとシュンペーターのビジョンの復権」というテーマに、まだまだ不十分ながらも筆者なりに磨きをかけた結果でもあります。
もっとも、そうした方向性は、どうやら筆者独自のものというわけではなさそうです。例えば、本書第6章でも紹介した新シュンペーター学派のカルロタ・ペレスの弟子に当たるマリアナ・マッツカートはその近著『ミッション・エコノミー』で、自身が提唱するイノベーションを目的とした政府の積極的な支出を正当化する理論としてMMTに言及するとともに、自らのアイデアに影響を与えた人物の1人としてMMT派のステファニー・ケルトンを挙げています。
かたや、本書第4章でも述べたように、理論上は財政の自動安定装置を重視するMMTの主唱者たちも、大きな課題の解決に向けた裁量的財政政策を主張するようになっています。いずれも主流派の殻を打ち破った20世紀経済学の二大巨頭であるケインズとシュンペーターの融合が、本書第6章で詳述したコンドラチェフ・サイクル1周期分の時を経て起きつつあるのかもしれません。
いずれにせよ、MMTの不完全さは、決してその存在意義を否定するものではありません。むしろ不完全であることで、主流派経済学に代わる将来のパラダイムの基礎として、MMTを研究する意義をより一層高めているのではないでしょうか。
筆者は、第1章で「日本の現実に根差してMMTを研究あるいは応用することは、経済学の発展への少なからぬ貢献となるのかも」と述べました。それは、決して自分に言い聞かせたわけではなく、そうした意義を感じてMMTを真剣に研究しようという人が増えることへの期待を込めたものです。本書がそうした方々の一助となれば、著者として喜びに堪えません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

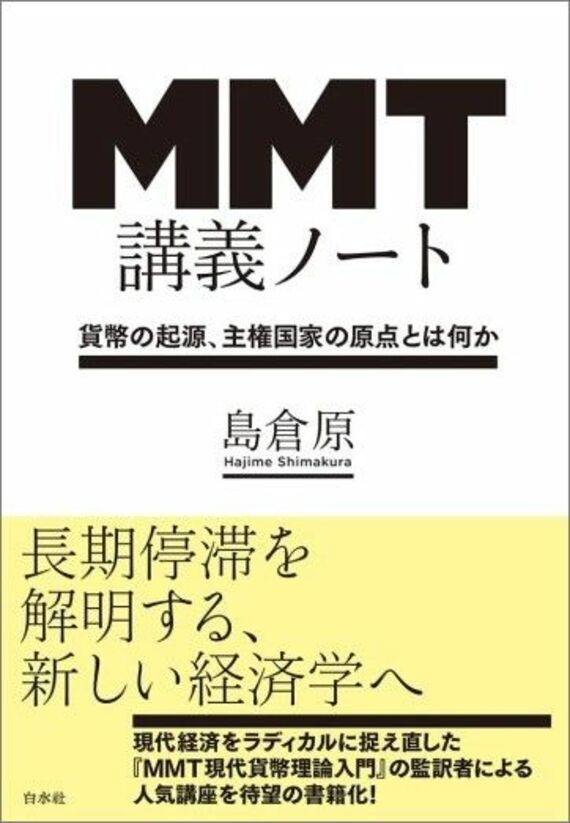






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら