地方銀行の体力差はどれくらいあるのか。最新決算から不良債権比率のワーストランキングを作成。健全性を見るうえで重要な指標だ。

2020年度の地方銀行の決算で相次いだのは、「予防的な引き当て」だった。これは将来発生しうる貸し倒れの費用を前倒しで計上するもの。銀行がこうした対応を取るのは、「足元で倒産は増えていないが、企業の業況悪化から不良債権比率は着実に上昇している」(地銀幹部)からだ。
下の表は、不良債権比率が高い順に地方銀行100社を並べた。1位は静岡県のスルガ銀行。シェアハウス問題によって不良債権比率が高止まりしている。足元では、アパートやマンション向けのローンについて弁護団が立ち上がり借金の帳消しを求める動きがあり、予断を許さない状況だ。
コンコルディア・フィナンシャルグループでワースト4位の東京都の東日本銀行のように不良債権比率が大幅に上昇した銀行もある。これは一部融資先に対して予防的引き当てをしたことで債権分類が悪化し、不良債権額が増加したためだ。今後コロナの影響が顕在化してくると、同様の動きが増えてくる可能性は高い。
銀行が健全性を維持するうえで、自己資本比率の高さを合わせてみることも重要だ。不良債権比率が高く、自己資本比率が低いところは注意すべきだろう。



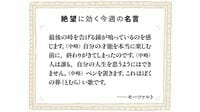






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら