
業界最大手は「保険適用」見送り
「保険診療では最高の医療を提供できない。自由診療を継続し、ほかでは授かれなかった患者さんの最後の砦になる」――。不妊治療クリニック最大手の一角、リプロダクションクリニックのCEO・石川智基医師は、4月以降も同クリニックでは自由診療のみを行う理由をこう説明した。
では、なぜ保険診療では最高の医療を提供できないのか。「薬の量を増やしたり、注射の回数を増やしたりしないと、妊娠できない患者さんがいる。当院はこれまでそういう人たちにきめ細かな治療をしてきたが、保険診療になるとそれが認められない。われわれが提供する治療のクオリティを保つための決断だ。売り上げはいったん減ると思うが、それよりプライドの問題」と石川医師は話す。
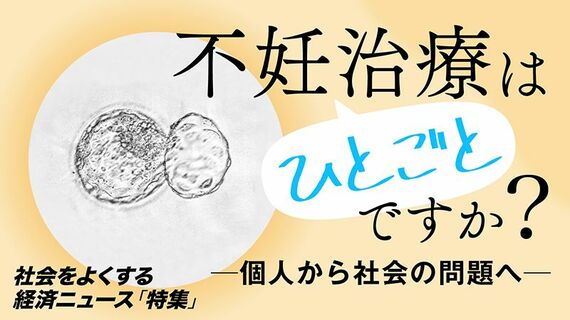
日本では混合診療(健康保険の範囲内の治療は健康保険で賄い、範囲外の治療については患者自身が費用を支払うこと)が認められていない(一部の先進医療に例外あり)。
また、保険診療では検査や治療ごとに価格が決められ、最新の医療機器を導入するなど保険診療の範囲を超えた治療を行っても価格に転嫁できない。そのため、治療の自由度を追求したい同クリニックでは、保険診療を見送った。

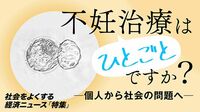





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら