
一定数の需要がある限り、稼働をゼロにはできない
――まず現在のタクシー業界が置かれた現状をどう見ていますか。
例外なく多くのタクシー会社が苦しんでおり、売り上げも5~6割程度に落ちている。
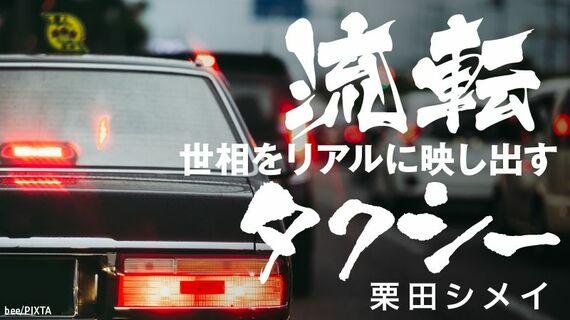
この業界は移動してなんぼの世界で、その根幹となる移動の自粛を促すわけですから、形態として成り立っていかない。ただ、公共交通機関としての役割があり、一定数の需要がある限り稼働をゼロにできない。そこにジレンマがある。
――実際に現場のドライバーや会社からも「休めるなら休みたい」という声も多かったです。
確かに休みたいという人も多いけど、それを国がどういう形で支援するか、という問題も生まれる。この業界の肝は、労働集約型産業であるということ。従事する乗務員の生活や家族を守るために、休業手当は必要だ。
なぜならこの業界の基本は歩合制で、例えば月12勤務で36万円稼いでいた人がいたとして、それが半額になると生活できるのか。おそらく難しいでしょう。そのために雇用調整助成金をしっかりと申請して、雇用を確保すること。これが現状のコロナ禍における、一番効率的な方法でもあり、われわれからも業界には要望を出している。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら