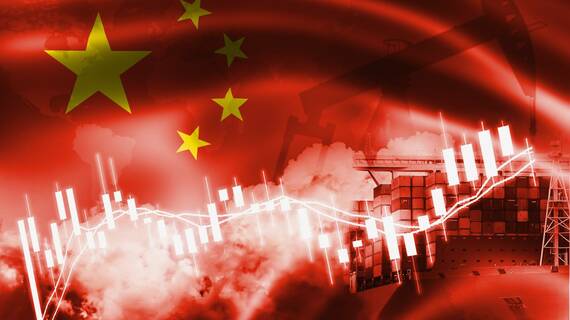
ピルズベリー「中国2049」に違和感
マイケル・ピルズベリーはアメリカを代表する中国通だ。2015年に出版された著書『China2049』は、世界中で話題になった。

その本で著者は「遅れている中国を助けてやれば、中国はやがて民主的で平和な大国となると思っていたが、彼らは当初より2049年に世界に君臨する『覇』を目指しており、アメリカはまんまと中国にだまされた」といった趣旨のことを述べている。
そして今、このトーンはアメリカの主流の意識になっている。筆者は、「歴史の一時代や事件は必然ではない」と思っているので、このトーンに違和感を覚えた。
その違和感をさらに説明するために、回り道になるが、中国文革以降の「改革開放政策」の沿革を駆け足で顧みたい。
10年にわたった文革の動乱、中国経済は衰退した。中国の改革1.0はその経済を立て直すために始まった。当初の改革は、国有企業の権限拡大を認めることから始まったが、「商品市場」自体がなかった時代では効果は上がらず、鄧小平は改革の重点を農村に移した。
そこで行ったことは、1950年代「大躍進」の疲弊から救った「農家請負制度」の再活用で、その徹底が農村における生産力を一気に高めた。また集団所有の「郷鎮企業」を奨励したため、農作機械、食品加工、土木建築など地場の需要にマッチした郷鎮企業が雨後のたけのこのように生まれた。
吸収された余剰労働力は、10年間で1億人に達したと言われ、1990年には中国全工業総生産高の35.6%になり、徐々に認められた私企業や外資、合弁企業を入れると、全体の45.4%までになった。これは旧東欧社会主義諸国と異なるところだ。
鄧小平はまた、深圳、アモイなど沿岸地方に経済特区を作り、外資優遇策政策により華僑や外国資本の導入を促した。1980年代初め、日本からは日立製作所がテレビ組み立て工場を福建省に、三洋電機が家電工場を深圳に進出し、注目された。




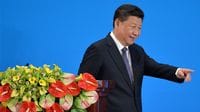




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら