岩田健太郎「感染症の最前線で働く激しい恐怖」 コロナ禍の今「レストン事件」を振り返る
ナンシー・ジャックスと彼女の夫でやはりユーサムリッドの専門家のジェリー・ジャックスの共闘も興味深く読んだ。特に興味深かったのが、彼らが「ホット・ゾーン」にいる描写だけではなく、彼らの平穏な私生活も描かれていたことだ。
彼らにも家庭があり、子どももいる。家に帰ればくつろぐし、睡眠をとったり、食事もする。そのような日常に生きる彼らも「ホット・ゾーン」に入るとき、非日常に入るときは命に関わる緊張感を突如強いられる。
そして、ナンシーが体験したように、ちょっとした切り傷、ちょっとした手袋の破れが生命の危機を意味するのだ。ぼくも、ぼくの妻も感染症の専門家だが、平穏な夫婦や子どもたちとの生活と、自らの生命の危機も頭をよぎるリスキーな瞬間が同居する。とても、感慨深い描写と構成だと思う。
「九死に一生を得た」看護師
2014年から2016年にかけて、これまでエボラが一度も流行したことがなかった西アフリカ諸国で巨大なエボラ感染症のアウトブレイクが発生した。ぼくも2014年12月から翌年1月にシエラレオネの流行地帯に入り、感染症専門家として病院の感染治療や予防の支援をした。
ある日、国際赤十字の治療センターにヨーロッパの看護師と一緒に入り、患者のケアをしたのだが、突如、点滴輸液をしていた患者の血管内カテーテルが抜けて、患者の血液が看護師の体に飛散した。これまで冷静にてきぱきと仕事をしていた彼女は悲鳴を上げ、そのときの恐怖の顔をぼくは忘れることができない。おそらくぼくも同じような顔をしていたことだろう。
彼女は翌日、医療脱出(メディカル・エバキュエーション)の対象となり、ヨーロッパへ飛行機により緊急搬送された。幸い、感染はなかったと聞いたがまさに「九死に一生を得た」のだった。手袋の破れたナンシーの恐怖はよく理解できる。
ジャックスやジョンスンたちが活躍した1989年のレストン・エボラ事件から30年以上が経っている。いろんなことがその間にわかってきた。
例えば、ナンシー・ジャックスやジョンスンが「実験室の中でサルの実験で」証明したと考えていたエボラやマールブルグの「空気感染」だったが、現実世界ではほとんど発生しないことがわかっている。そして、フィリピンから輸入された「レストン型」のエボラ・ウイルスは、実はアフリカのエボラと違って人間には病原性がない、サルにだけ病気を起こすウイルスだったことも判明した。

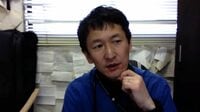






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら