岩田健太郎「感染症の最前線で働く激しい恐怖」 コロナ禍の今「レストン事件」を振り返る

初めて読んだのは20年前のこと
今回、解説を書くよう依頼されて本書のゲラを開いてみた。すぐに思い出した。『ホット・ゾーン』を初めて読んだのはぼくが医学生だった1990年代前半のいつかである。英語の原書で読んだか、高見氏の翻訳で読んだのか、いや、両方だったか。そこは、とんと思い出せない。
あのころ、ぼくは一介の医学生に過ぎず、感染症についてはあまりに無知だった。そのことは、数年後に沖縄県立中部病院研修医になった初日に感染症科をローテート(研修医が病院で各科を順に回って研修すること)し、日本臨床感染症界のパイオニアである喜舎場朝和先生に「お前のプレゼンは何を言っとるか全然わからん」と激怒されたことからも明らかだ。
当時のぼくは医学生的な微生物の知識や抗菌薬の知識はあったが、それが「感染症」という概念をもって形成されてはいなかったのである。
だから、そんな感染症に無理解だった医学生のぼくが『ホット・ゾーン』を初めて読んだとき、その内容を十分に理解したかというと、甚(はなはだ)心もとない。再読してみて当時気づいていなかったであろう発見が多々あった。貴重な読書体験であった。
もちろん、本書を読むのに特段の専門知識は必要ない。リチャード・プレストンの文章は活気にあふれて読みやすいし、専門書のような冗長さ、難解さはまったくない。それは日本語の訳文も同様だ。

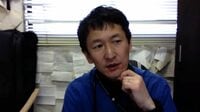






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら