恐怖の伝染病「ペスト」はこうして始まった 話題の小説の冒頭部分を一部公開(後編)
しかもその同じ日の正午、医師リウーは、アパートの前に車をとめると、街路のはずれに、門番が、首をうなだれ、両手両足を広げ、あやつり人形のような格好で、難儀そうに歩いて来るのを見たのである。老人は1人の司祭の腕につかまっていたが、その司祭は医師も知っている顔であった。パヌルー神父という博学かつ戦闘的なイエズス会士で、彼も時々会ったことがあり、市では宗教上のことに無関心な人々の間にさえなかなか尊敬されていた。
医師は2人を待った。ミッシェル老人は眼をぎらぎらさせ、せいせい息をきらしていた。どうも体の調子がよくなかったので、外の空気に当ってみようと思った。ところが、首と腋の下と鼠蹊部に激しい疼痛(とうつう)が起って、引き返さねばならなくなり、そしてパヌルー神父の助けを乞わなければならなかった。
ミッシェル老人を襲った「異変」
「どうも腫物(できもの)だね」と、彼はいった。「えらく骨が折れたよ」
車の戸口から腕を出して、医師はミッシェルの差し出す首の付け根のあたりを指でさぐった。一種の木の節くれのようなものが、そこにできていた。
「寝て、熱をはかっといてください。今日、午後から来てみます」
門番が行ってしまうと、リウーはパヌルー神父に、例の鼠の騒ぎについてどう考えているか尋ねた。
「なに」と神父はいった。「きっと流行病でしょう」、そういって、彼の眼は丸い眼鏡の陰で微笑した。
夕刊の呼び売りは鼠の襲来が停止したと報じていた。しかし、リウーが行ってみると、病人は半ば寝台の外に乗り出して、片手を腹に、もう一方の手を首のまわりに当て、ひどくしゃくり上げながら、薔薇色がかった液汁を汚物溜めのなかに吐いていた。しばらく苦しみ続けたあげく、あえぎあえぎ、門番はまた床についた。熱は39度5分で、頸部のリンパ腺と四肢が腫脹(しゅちょう)し、脇腹に黒っぽい斑点が2つ広がりかけていた。彼は今では内部の痛みを訴えていた。
「焼けつくようだ」と、彼はいっていた。「こんちくしょう、ひどく痛みゃがって」
黒ずんだ口のなかで言葉はくぐもりがちに、目玉の飛び出た目を医師のほうに向けていたが、その目には頭痛のために涙が浮んでいた。女房は、じっと黙りこんでいるリウーを不安に堪えぬ様子でながめていた。
「先生」と、女房はいった。「いったい、なんでしょう、これは」
「さあ、いろんなふうに考えられるんでね。しかし、まだなんにも確かな兆候はない。晩まで、絶食と浄血剤だ。うんと飲みものをとるようにしなさい」
ちょうど、門番はのどがかわいてたまらないところだった。
家に帰ると、リウーは同業のリシャールという、市内で最も有力な医者の1人に電話をかけた。
「いや」と、リシャールはいった。「べつに、とくべつ変ったことは目につかなかったが」
「局部的な炎症を伴った熱っていうようなものは、なかったですか」
「そうだ、あったよ、そういえば。2件ばかり、リンパ腺につよい炎症が来ててね」
「異常にですか」
「さあね」と、リシャールはいった。「普通っていうと、なにしろ……」
いずれにしても、その晩、門番はうわごとをいいはじめ、40度の熱を出しながら、鼠のことを口走った。リウーは膿瘍(のうよう)固定を試みた。テレビン油のしみる痛みに、門番はうなった――「ああ、畜生!」
リンパ腺はさらに大きくなり、さわってみると堅く木のようになっていた。門番の女房はおろおろしていた。
「ずっとついててあげなさい」と、医師は女房にいった。「それで、呼んでください、もし何かあったら」



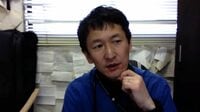




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら