恐怖の伝染病「ペスト」はこうして始まった 話題の小説の冒頭部分を一部公開(後編)
翌4月30日は、もうなま温かい微風が、青くしっとりした空に吹いていた。風は花の香を運んで、郊外のずっと遠くのほうからもそれが漂って来た。街々の朝の物音はふだんより一層生きいきと楽しげに聞えた。
1週間を暮してきた暗黙の懸念から解放されて、この小都市の町じゅう、この日はおよそ一陽来復の1日であった。リウー自身も、妻から手紙があったのでまず安心して、軽快な気持ちで門番のところへ降りて行った。そして、事実、朝になって熱は38度に下っていた。衰弱して、病人は床のなかでほほえんでいた……
「だいぶいいようだけど、どうでしょう、先生」と、女房はいった。
「まあ、もう少し様子をみないと」
「鼠のやつ!」と、病人はいっていた
ところが、正午になると、熱は一挙に40度に上り、病人は間断なく譫言(うわごと)をいい、吐き気がまた始まった。頸部のリンパ腺は触れると痛そうで、門番は頭をできるだけ体から遠くに離していようとでもしているようだった。女房は寝台の足もとに腰掛けて、両手でふとんの上から、そっと病人の足を押えていた。女房はリウーの顔を見守っていた。
「どうもこいつは」と、リウーはいった。「こいつは隔離して、まったく特別な手当てをやってみる必要があるな。病院に電話をかけるから、救急車で連れて行こう」
2時間の後、救急車のなかで、医師と女房とは病人の顔をのぞき込んでいた。いちめん菌状のぶつぶつでおおわれた口から、きれぎれの言葉がもれていた――「鼠のやつ!」と、病人はいっていた。
土気色になり、唇は蝋(ろう)のように、まぶたは鉛色に、息はきれぎれに短く、リンパ腺に肉を引き裂かれ、寝床の奥にちぢこまって、まるでその寝床を体の上へ折りたたもうとするかのように、もしくはまた、地の底から来る何ものかに一瞬の休みもなく呼びたてられているかのように、門番は目に見えぬ重圧のもとにあえいでいた。女房は泣いていた。
「もう望みはないんでしょうか、先生」
「死んでしまった」と、リウーはいった。
******
その後、『ペスト』では同様の熱病者が続出し、次々と市民が命を失っていく。感染拡大を防ぐために街は外部と遮断され、封鎖状態に。行政は対応に後れを取り続け、ペストの脅威は拡大の一途をたどっていくのであった……。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

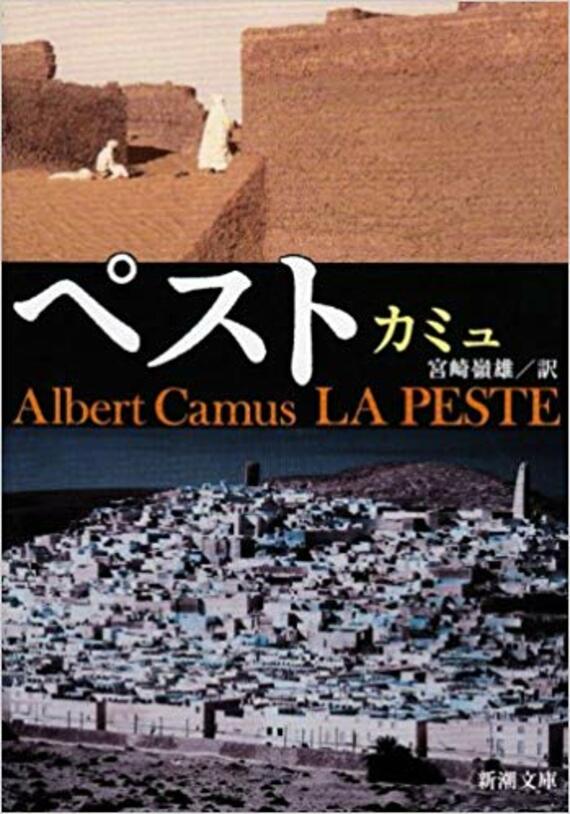


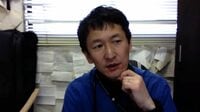




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら