6.2%成長の中国、27年ぶり「低成長」のわけ 習主席が警戒する「灰色のサイ」がやってくる
ところが、この政策が資金の目詰まりを起こすことになった。インフラ投資のための会社をつくろうにも、資本金がないと銀行は貸せないからだ。そこで6月初めに制度を改正し、専項債で調達した資金を資本金に充当することが認められた。そして資本金の5倍まで銀行借り入れができることになった。今後はこれでインフラ投資にはかなり勢いがつくとみられる。
中国では毎年7月下旬に開かれる共産党中央政治局の会議で、下半期の経済運営の方針が議論される。今年もその場で、景気下支えのためのインフラ投資の拡大に向け、さまざまな政策が決定されるとみられる。これでうまくいけば下期は6.5%、通年で6.4%程度の成長率が期待できるかもしれない。もしトランプ政権による第4弾の制裁関税が発動されるようなら、専項債がさらに増額されることだろう。
懸念材料は、これにより債務問題が再燃することだ。中国の非金融部門の債務は拡大を続け、2018年12月末時点でGDP比254%まで膨張している。習近平主席は今年1月の談話で、企業と地方政府の過剰債務問題を「灰色のサイ」に例えた。
「反腐敗運動」で地方政府は委縮気味に
予測困難だが発生すると破滅的な結果をもたらす「ブラックスワン」に対して、灰色のサイとは発生確率が高く打撃も大きいのに見逃されがちなリスクを指す。債務拡大を伴うインフラ投資は、米中摩擦のもとでの景気底割れは防げても、灰色のサイをもっと太らせるリスクがある。
こうした懸念がくすぶる中で「5倍までレバレッジをかけていい」と言っても、そこまで銀行が融資をつけてくれるのかはわからない。2013年に習政権が発足して以来の反腐敗運動で、地方政府の現場が委縮しているという要素も見逃せない。こうしてみると、頼みの綱のインフラ投資が期待通りの効果をあげる保証はない。
リーマンショック後に中国は4兆元政策でV字回復を果たしたが、当時はGDPの5割近くが投資だった。現在は消費のウエートが高まり、4~6月期の成長率をみても最も寄与度が大きかったのは消費だ。6.2%成長のうち3.7%が消費の伸びによるもので、純輸出の1.3%、投資の1.2%がそれに続いている。
ここまで大きくなった経済を持ち上げるのに、インフラ投資頼みでは限界がある。企業が自信をもって投資をし、家計が消費に前向きになれるようなビジョンを打ち出せるか。貿易摩擦の長期化をにらんでアメリカとの持久戦を呼びかける中国政府にとって、それが最大の課題だろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

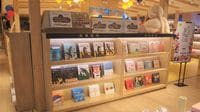































無料会員登録はこちら
ログインはこちら