
例えば業務効率を改善するアイデアを思いついたとき、それを実現するには既存の業務フローを変更し、システムの改修や新規開発が必要になるとする。社内では情報がすべてオープンに共有されている。開発を進める中で、その取り組みは業務効率化の分野で一目置かれているA氏の目に留まり、やがて率直なフィードバックを受けることになるだろう。
このような状況で、自分のアイデアを実現するためにどこまで本気で取り組めるだろうか?
近年、多くの企業で「情報の見える化」、つまり社内の透明性を高める取り組みが進んでいる。例えば米Netflix(ネットフリックス)共同創業者のリード・ヘイスティングス氏は著書『NO RULES』で「情報は可能な限り共有すべきだ」と述べ、透明性を「サンシャイニング」と称し推進している。
筆者、大阪経済大学の林田修氏、専修大学の森田公之氏の共同研究では、情報をオープンにしすぎることが、かえって新しいアイデアやイノベーションを阻害する可能性を示した。本稿ではその研究を基に、「透明性とイノベーションの関係」について紹介したい。

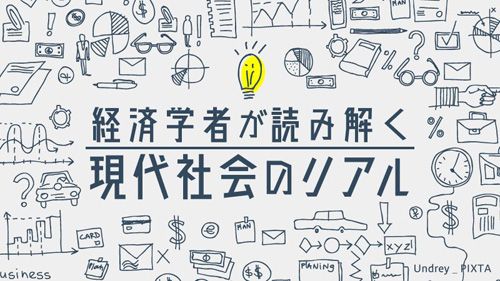

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら