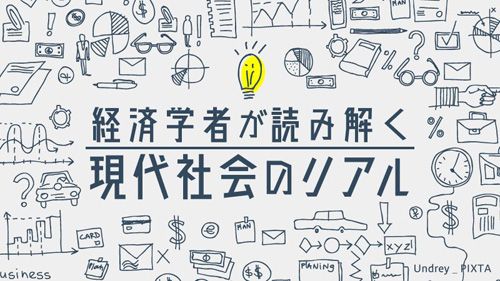税制改革は世の中の大きな注目を集める。「年収の壁」や「消費税減税」は選挙の大きな争点となった。2010年代は法人税率引き下げの時代だった。法人所得には国税の法人税だけでなく法人住民税や法人事業税も課されるが、これらを合計した法定実効税率は11〜18年度に、大企業(資本金1億円超)は39.54%から29.74%に、中小企業(資本金1億円以下)は40.87%から33.59%に引き下げられた。
とりわけ安倍晋三政権下で行われた14年度以降の改革の特徴は、法定実効税率を減じる一方、税収確保のため大企業に対しては「外形標準課税」の拡大が行われたことである。外形標準課税とは、人件費を含む付加価値や資本金を課税標準とする税で、法人事業税(地方税)として課されている。対象は資本金1億円超の大企業だ。
法人税は収益がある企業、つまり「稼ぐ力」のある企業の負担が大きい。一方、外形標準課税は収益がない企業も含めて広く薄く負担を分かち合う仕組みである。政府はこの改革を「成長志向の法人税改革」と呼び、企業の稼ぐ力の向上を狙った。しかし改革以降、企業の内部留保や現金・預金の増加に比べて設備投資や賃金の伸びは緩やかであったため、改革の効果に疑義が呈されるようになった。