ここまで決め方をご紹介してきましたが、あまりにも決めることが多すぎると「意思決定疲れ」を起こしてしまいますので、意思決定の機会自体を減らすことも重要です。
皆さんもよくご存じのスティーブ・ジョブズ氏がいつも同じ服装だったり、イチロー選手がバッターボックスに入る前に決まった動きをする例に代表される「ルーティン化」がこれに当たります。ルーティン化は余計な意思決定を減らして、重要なことだけに意識を集中することを目的としています。
これも注意点を述べるとすれば、人によって何が余計な意思決定かは違うということです。ファッションが好きな人が毎日同じ服装をしてもモチベーションは下がっていきますし、毎回同じ手順で仕事をしようとした場合、もしかすると良い発想や改善ポイントを見逃すことになるかもしれません。
ルーティン化は、他の選択肢の可能性を捨てることを意味します。自分にとって重要なこと、集中すべきことが何かを理解していなければ、可能性を捨てることはできません。意思決定は何をすべきかを選ぶことと同時に、何をしないかを選ぶことでもあります。つまり、ルーティン化は意思決定を減らすのではなく、自分にとって本当に重要なことを決めた結果として、起こることなのではないでしょうか。よって、闇雲に人のルーティンを真似てみても思うような効果は得られないでしょう。
今は、情報過多の時代ですから、「あれもすべき、これもすべき」とすべきことが山のように目の前に積み上がっているように見えます。それをすべて鵜呑みにしていては、本当に自分が何をしたいのかがますます見えなくなってくるでしょう。「私のルーティンはこれだ」と胸を張って言えるように捨てる覚悟を持ちたいものです。
最後は判断ではなく、決断
いろいろと意思決定のテクニックについて、ご紹介してきました。ここで敢えて言いますが、この方法を使えばいつでも正しい意思決定ができるということは絶対にありえません。正解のない予測不能な世界になった今、絶対的に正しい選択肢があるわけではないのです。
だからこそ言えるのは、過去の情報から判断をするという決め方ではなく、自分がこうしたい、こういう未来にしたいという「意思」が重要ということではないでしょうか。自分が納得のいく選択をしたという自信が行動につながり、その選択肢が正しいものに結果的になります。ご紹介した意思決定の方法が、皆様の次の一歩を踏み出すものになることを願っています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

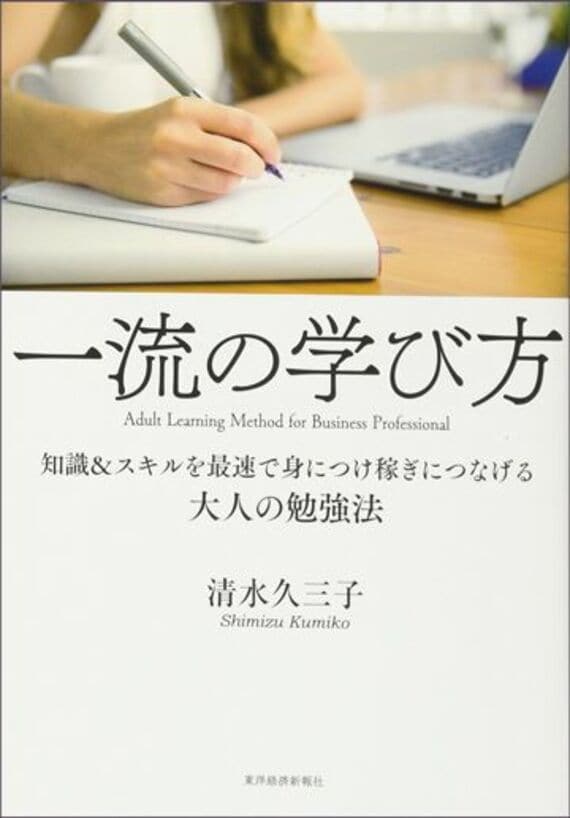






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら