山口絵理子が探し続ける「輝ける場所」とは? マザーハウスが起こしたモノづくりの奇跡
しかし、働くほどに、一つの疑問が生まれてきた。
「援助って、本当に求める人の手に届いているのかな……。そんな疑問に答えるには、現場に行くしかないのでは?」
と、何も知らない私は思った。
インターネットで検索をかけた。
“アジア 最貧国”
今、それをしていたら、違う国が出てくるので、運命ってすごい。2003年当時、そこには、“バングラデシュ”という国名が映し出された。
(行ってみよう)
私は、2週間という短いバックパック旅行をする。しかし、この2週間が再び運命を変える。見るもの見るもの、自分が生きてきた世界と違う。国際機関でイメージしていたものより、ずっとずっとひどかった。
(どうして子供のお腹は出ているんだろう……)
移動手段であるリキシャ。私よりもずっと若い子たちが、汗だくで私を乗せて移動する。辞書を片手に、話せるチャンスがあったらたくさん話した。その度に日本をうらやましそうに語るベンガル人。
そして、
「自分たちの国は変わらない」
と私に教えてくれた。すべての瞬間が、私に決意させてくれた。
「2週間なんて短すぎる。この国の大学院に進もう」
なんて無謀で無計画!
そうして2004年から2年間、私はバングラデシュの首都ダッカで大学院生として過ごすことになった。今思えばなんて無謀、なんて無計画。けれど、当時の私は120パーセント真剣に、自分が生きる意味を考え、悩み、その先に行動することでしか、答えが見つからなかったのだ。
生きる意味は、すぐにはわからなかった。度重なるストライキや洪水。デモや賄賂の嵐。
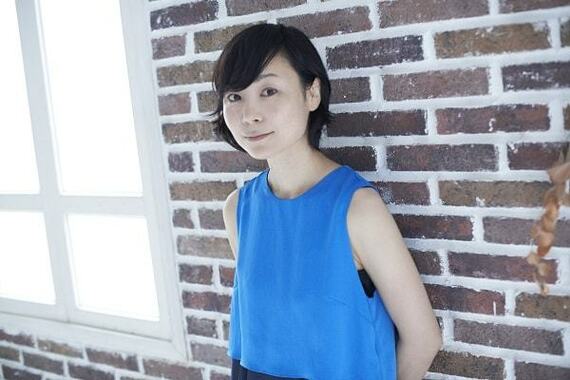
「かわいそうだ」
という気持ちはいつの間にか、
「この野郎」
という気持ちに変わっていった。
しかし、「ジュート(黄麻)」というバングラデシュの特産品である麻と出会ったことから、この国が持つポジティブな光に気がついた。
「貧しいって言われる国にも、光る素材もあって、光る職人さんたちもいる。私たち先進国の人たちが“貧しい”ってひとくくりにしているだけなんだ」
2005年、私は現地の素材を使った付加価値のあるものを、この国から生み出したいという、確固たる思いを持った。そして、その「もの」とは、ジュートが元々麻袋に使用されていた、という理由だけで、「バッグ」に決めた。不思議とほかのアイテムの選択肢は思い浮かばなかった。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら