「日本でも…」難治てんかん患者・家族が期待する"大麻由来成分CBD入り医薬品"アメリカで承認――サプリではすでに流通も、薬には「高い壁」が
2023年12月の国会で大麻取締法などの改正案が成立したときの付帯決議は、「処方は、研修の受講等の一定の資格を満たす医師が行う」ことを検討課題に挙げている。
舩田さんも運用方法については今後の課題としつつも、「使用する患者さんを医療機関側が登録するなどのしくみが必要」と考える。
大麻から医薬品が生まれる日が来るとすれば、国が定めたルールに則って承認され、医師の処方により使用するものとなる。
承認後も、副作用や他の医薬品との相互作用、そして長期使用の影響などについて、慎重かつ詳細な情報収集が必要だ。医療現場、製造販売企業、厚生労働省が連携して対応することが求められる。黒岩さん(前出)の言葉を借りるなら、基本的にはほかの薬と変わらないのだ。
サプリメントやスキンケア商品は?
最後に、すでにCBDを含有する製品(医薬品でないもの)がサプリメントやスキンケア商品として流通しているという“事実"についても触れておきたい。
もともと、大麻草の種子や成熟した茎に由来する製品は流通可能で、法改正後もTHCの残留が基準値以下なら規制対象外となる。これらは我々消費者が自分の意志で購入し、日々の健康の維持・増進や美容に役立てる、という位置づけだ。
一方で、2023年の国会の付帯決議(前述)には、次の文言が盛り込まれた。
<CBDを使用した製品について、安眠等の機能を過度に強調した広告で消費者が惑わされることのないよう、(政府は)監視指導を行うこと>
消費者側も、その製品にどんな成分がどれくらい含まれているか、気を付けて選びたい。もしも「摂取して体調の異変を感じたら、速やかに医療機関を受診すること」と、舩田さんはアドバイスする。
その際、製品やパッケージの情報を提供するのがよいという。消費者がCBD製品を安全かつ安心して使用するために、第三者による安全性の評価機関などの構築も重要になるだろう。
大阪の医薬品メーカー・モリモト医薬の代表取締役で、国内外の製薬企業やCBD関連企業とコンタクトをとっている盛本修司さんも、「主要な成分の含有量やほかの成分が入っていないか、品質をしっかりと管理する必要がある」と指摘する。
大手製薬会社出身の盛本さんは、大麻由来医薬品やCBD製品の適正な普及のため、静岡県立大学大学院客員教授の佐藤均さんらとともに、産学連携コンソーシアムを立ち上げた。企業や研究機関が参画し、ともに研究開発し、産業育成するイメージだという。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




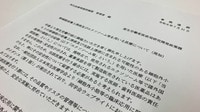


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら