中国王朝・隋の時代、嫉妬に狂った皇后が色恋だらけの後宮でまさかの「一夫一婦制」を実施 罪のない者の死、皇帝の"奇行"…招いた波乱の数々
607年、煬帝が帝位について4年目。倭国から2回目の遣隋使が来た。小野妹子が煬帝に渡した国書には、『隋書』によると以下のような文句が書いてあった。
「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無(つつがな)きや」
太陽が昇る国の天子から、太陽が沈む国の天子に、お手紙を差し上げます。お変わりありませんか、という意味である。
煬帝は不機嫌になり、役人に「野蛮人の手紙に無礼な文言があったら、今後は自分に見せるな」と命じた。倭国は未開の小国のくせに、中華帝国と対等の口をきく。しかも「太陽が沈む国」などと、隋の没落を暗示する不吉な言葉を使ったからだ。
煬帝は暴君? 語り継がれる悲惨な最期
不吉な言葉は、現実になった。大分裂時代の余燼(よじん)は、まだ冷えていなかった。
その後、隋は反乱が相次いだ。618年、煬帝は、12歳のわが子が斬り殺されるのを目のまえで見たあと、自分は首を絞められて殺された。50歳だった。隋は滅亡した。
煬帝は並外れた暴君で、奢侈(しゃし)と荒淫にふけって国を滅ぼしたとされ、いろいろな物語が伝えられている。ただし、後世の粉飾も多いようだ。煬帝がめとった后妃の数は10人ていどにすぎず、息子は3人、娘は2人と、もうけた子どもの数も、歴代の皇帝にくらべれば少ないほうである。
煬帝の娘は隋の滅亡後も生き残り、うち1人は唐の第二代皇帝・太宗の妃となった。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

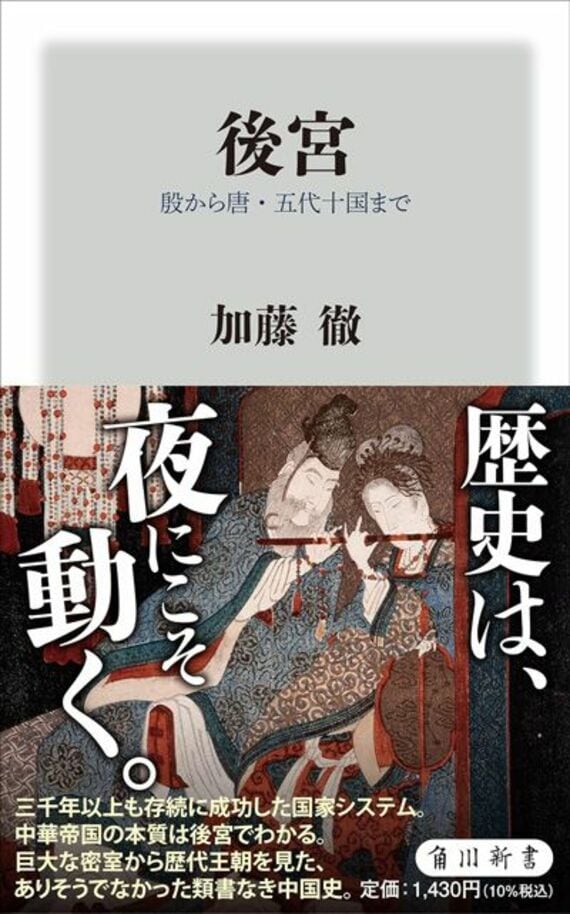































無料会員登録はこちら
ログインはこちら