「日本語を勉強して。それが未来の言語だから」吉本ばななや三島由紀夫を訳した仏人女性。《55年前の大阪万博》の年に開けた数奇な翻訳人生
「驚いたのは読者層が広かったことです」。男性女性、年配者も若者も皆がサインをもらう列に並んでいた。私が『キッチン』を初めて読んだときは、少女向きの良い作品だと思いましたが、フランスのさまざまな年代の心に響いていたのです」
ばななさんは時間をとってそれぞれの人に「小説はお気に召しましたか?」と聞き、名前を聞いてからサインをしたそう。
「ある若い女性読者が『ばななさんの本を読んで私の人生が変わりました』と言ったのをよく覚えています。また、別の年配の人は『この本を読まなかったら私は自殺していたかもしれません』とも」
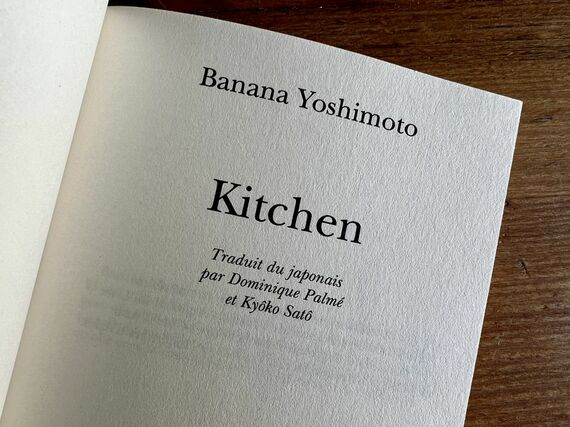
「私はあくまでも翻訳家」
ドミニクさんはあるとき、日本に招待された講演会で、著名な仏文学の評論家と自分が同等に扱われ、そこまで認められる存在になったのかと驚いた。評論家としての意見を求められることもある。
「認められる存在に」と計算して仕事をしてきたのではない。目の前のことをひとつひとつ丁寧にこなしてここまでたどり着いた。しかし、ドミニクさんは「私はあくまでも翻訳家です」と強調する。
そして翻訳のモットーは、20歳の頃から変わらない。彼女自身は黒子であり、読者には翻訳された本の舞台や筆者に思いを馳せてもらいたい。そのために、誰にでもわかる平易な言葉で書くこと、難しいことでも簡単な言葉で本質的なことを伝えられるよう奮闘している。

「私は好きではない作品の翻訳は断ると思います。なぜかというと、好きなものしかうまく訳せないから。だから、愛情を持てなければ何もできません」
最近では、多和田葉子『献灯使』を翻訳。多和田さんの著作はドイツ語から各国語に翻訳されることが多かったが、初めて日本語から直接フランス語に訳された。2023年にはフランスで外国人女性作家と、その翻訳家を支援することを目的としているフラゴナール文学賞を受賞。作家だけではなく、翻訳家のドミニクさんも評価されたと嬉しそうに教えてくれた。
「残りの人生は、自分の好きな本の翻訳に費やしたいです」
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


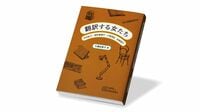




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら