「日本語を勉強して。それが未来の言語だから」吉本ばななや三島由紀夫を訳した仏人女性。《55年前の大阪万博》の年に開けた数奇な翻訳人生


「彼岸花」「特急白鳥」どう訳す?
「料理にも味付けが必要ですが、翻訳における味付けはなんだと思いますか?」
これはドニミクさんが過去に翻訳学の授業を持ったとき、生徒へ問いかけた言葉だ。
「翻訳に大切なエッセンス、それは作家と作品への愛情です」
ドミニクさんの言葉に、生徒たちは目を丸くして聞き入った。
「だから皆さんは、まず最初に作家の一番良い読者になってください」
前述したように、ドミニクさんはたった1行の翻訳に数日かけることがある。
例えば「彼岸花」。この花の名前をどのように訳したら、日本語の持つ情緒が伝わるだろうか。
もしくは小説の中に「特急白鳥」という電車の名前が出てきたら?
まずドミニクさんは、その特急が実在するかを調べる。小説の内容をふまえ「ひょっとしたら白鳥座に関係があるかも」とひらめくと、とにかく調べる。そして七夕の伝説に行きつき「日本の織姫と彦星の物語とかけているのかも」と思う。でも、はたしてその読みが合っているのか?
「だめだ、失敗するかもしれない」と時々不安に駆られる。
そんなときはディテールにこだわらずに、2つの可能性を考えて訳し、パリ在住の日本をルーツに持つ翻訳仲間に読んでもらい、意見を聞く。
まるで謎解きのような作業を繰り返し、1行の翻訳に数日、1章を訳すのに数カ月かかることもあるのだ。でもそれがたまらなく楽しい。「締切がなくて、一生翻訳だけをやっていられたら」と言う。
精査しながら、日本語の文章が持つリズムや音楽性を崩さないように、フランス語に翻訳する。大切にしているのは、誰にでもわかる平易な言葉で書くこと。「難しいことでも簡単な言葉で本質的なことを伝えられます」。
「AIの台頭は大惨事」だと言う。
「例えば三島由紀夫は古い漢字や、日常生活であまり使われていない単語をわざと使っています。AIで調べてみると、そのような言葉は見つかりません。AIはものすごく限られた、少ないボキャブラリーです。なんの味もありません」


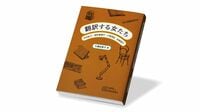




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら