エンジンも、低回転域から中回転域でのトルク感が増したと同時に、回転の伸び感がより強くなり、全体的にスポーティ性が増した印象を受ける。
筆者は1990年代後半から2000年代前半にかけて、アメリカでNBに乗る機会が多かったが、当時はNBをベースにスポーティな仕様に改良するアフターマーケットパーツがよく売れていたものだ。
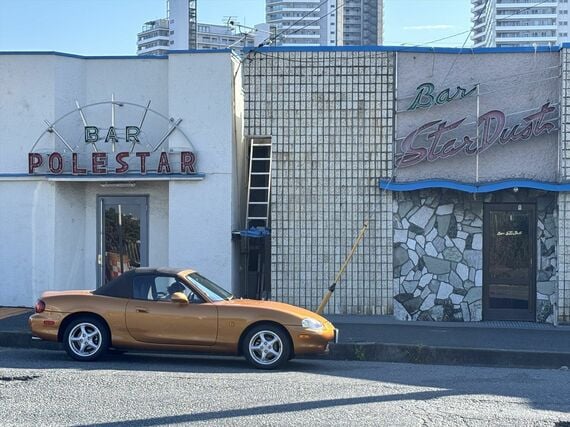
バックボーンフレーム構造のシャシーを含め、基本的な車体構造はNAを踏襲する部分が少なくないが、NBという「馬」での人馬一体は、NAとは少し性格が違うように感じる。
その翌日は3代目、NCの番だ。こちらもグレードは「RS」。走り出してすぐ、明らかに「馬」の種類が違うことを直感する。

ライトウェイト・スポーツカーであることに変わりはないが、2.0Lエンジン搭載の車体(プラットフォーム)の採用で、全体にどっしりとした風格がハンドリングからもしっかりとわかる。ドライビングポジションも、NA、NBと比べるとスポーティ性が増した印象だ。
NCは洗練された印象
エンジンのトルクバンドは広く、さらに高回転域が一気に伸びていく。NCの走り味は、全体がNA、NBよりも洗練されている。
筆者は、NCの発売前にアメリカ・ハワイ島で行われたマツダ主催のメディア向け国際試乗会に参加しており、その際に主査の貴島孝雄氏と、その後ND主査となる山本修弘氏から「NCが目指したこと」について現地でじっくりとお聞きした。

それ以降、各種の歴代ロードスターに乗る機会があり、そして今回、NA、NBと短期間に乗り継いだ後にNCに乗ったことで、貴島氏と山本氏が当時ハワイ島でメディアに伝えたかったことがやっとわかったように感じた。
トリは現行モデルとなる、NDだ。グレードは「S Leathre パッケージ・V Selection」。

NCからNDに乗り換えた日は、マツダR&Dセンター横浜でマツダが推進している次世代バイオディーゼルに関する技術説明会の日で筆者も参加。マツダが直面している環境対応施策の理解を深めるとともに、ロードスターの未来を思案した。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら